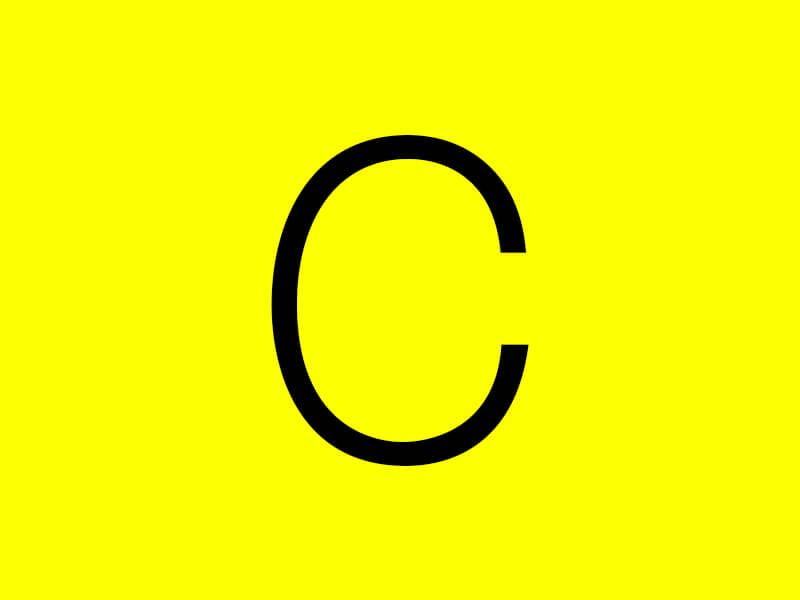マメ科のソラマメは、ふっくらとしていながら、ごつごつとしたシルエットが特徴的です。食卓に並ぶと季節を感じる食材でもあります。
新鮮なうちに調理して食べることが、美味しくいただけるコツでもあります。
そんなソラマメの栄養と効能について見ていきましょう。
スポンサーリンク
ソラマメの起源と歴史
ソラマメは地中海、西南アジアが原産地と考えられています。
大粒種のソラマメはアルジェリア周辺、小粒種のソラマメはカスピ海南岸が原産地という2つの説があります。古くは、イスラエルの新石器時代の遺跡から発見されています。
ソラマメは古代エジプトやギリシャ、ローマで食されていました。紀元前3000年以降中国に伝わり、日本には8世紀ごろ渡来した、と考えられています。インド僧の菩提仙那が、奈良時代の僧、行基(東大寺の大仏にかかわった僧)に贈ったのが始まりと言われています。
「ソラマメ」という和名の由来は、さやが空に向かって付く姿から「空豆(ソラマメ)」と付けられました。また「蚕豆」という字があてられた理由には、旬の夏と蚕に似ていることから付けられたとしています。
酒処では「天豆(ソラマメ)」と表示している場合もあります。
日本でソラマメは、明治時代から栽培が本格的に始められました。現在の品種については、アメリカやヨーロッパからの品種を試作したものになります。
日本では若さやを生で楽しむ食べ方から、乾燥させたソラマメを煮豆として楽しむ食べ方ができます。
ソラマメの種類
ソラマメには別名、ノラマメ(野良豆)・ナツマメ(夏豆)・テンマメ(天豆)・シガツマメ(四月豆)・コヤマメ(高野豆)といった呼び方があります。
そのほかにソラマメには、豆の大きさと形に違いがあり、大粒種長莢種があります。
大粒種 [一寸そら豆]

一寸は、さやの長さではなく豆の大きさを表します。豆がおよそ3cmほどになる大粒のソラマメで、マメサヤはずんぐりとしています。
国内のほとんどの地域で、もっとも生産されているのがこの大粒種になります。
サヤの形から別名「お多福豆」とも呼ばれ、現在では市場で販売されているソラマメの品種の主流になっています。
形がふっくらしていて、さやの中は大きさの揃っている粒であるものが良品とされています。
長莢種 (ちょうきょうしゅ) [さぬきながさやそらまめ]

長莢種は、1つのサヤに豆が6粒から7粒も入っている細長いソラマメです。草丈が低くて栽培が容易なことが特徴です。
四国地方で発達した品種で、香川県を中心に古くから栽培されています。
未熟豆は生食もできますので、取れたてのソラマメはサラダなどにも使うことができます。北アフリカ原産のソラマメは、日本でも明治期から栽培されています。
青果用として食べられているものは、未熟豆です。完熟豆は黒っぽくなり、煮豆や甘納豆などにします。
早生ソラマメ
小粒で早生のソラマメです。早生ソラマメは、千葉県を中心に作られていましたが、最近はあまり作られなくなっています。
最近はあまり市場で見かけない、レアな品種になっています。
種は販売されていますので、家庭菜園で作ったことがある人はいらっしゃるかもしれません。
初姫

ソラマメのさやは一般的なソラマメと同じ緑色ですが、中の豆が赤い品種です。
初姫のサヤは1粒から3粒入りのものがたくさんなります。粒の大きさは3cm程の大粒です。
表面の皮は赤いのですが、中は普通のソラマメと同じく黄緑色です。
味は、普通のソラマメよりもコクとほのかな甘みがあります。ご飯と一緒に炊き込むと、お赤飯のような色を楽しむことができます。
ソラマメの食感
ソラマメは茹でることで、ほっこりとした豆特有の食感を味わうことができます。茹でることで豆の旨味を味わうことができるソラマメですが、生で食べられる品種もあります。
ソラマメは、収穫期が早いものは糖分や水分がたっぷりで、豆はみずみずしく「しっとり」とした食感を楽しむことができます。
一方で、しっかりと熟したソラマメは発芽のために糖分がデンプンに変わり、ホクホクとしたジャガイモのような食感を楽しむことができます。
ソラマメにはサヤをむいたとき「へその緒」との接合部分を見ることができます。収穫期が早い未熟なソラマメは、この接合部が緑色ですが、完熟したソラマメは、接合部が黒くなっています。
サヤそのものも違います。未熟なソラマメのサヤは、まっすぐで新鮮な緑色をしていますが、完熟したソラマメは、表面がざらついて色褪せ、茶色に色付き始めています。
生で食べられるソラマメは、サクサクとした食感を味わうことができます。サラダに入れて楽しみましょう。
ソラマメの旬と有名な産地
ソラマメの旬は4月から6月になります。そして、最期の旬は7月になります。初夏にビールのつまみで使われることもあります。
この頃が一般的な旬の時期なのですが、九州の鹿児島県をはじめとする暖かい地域では、2月から3月頃には市場に出回るようになります。
ソラマメは九州から、四国・関西・関東地方へと北上します。広い地域での旬の時期は4月から6月の春から初夏にかけてになります。そして、最後に旬を迎えるのは6月から7月になります。
ソラマメは、青森県から鹿児島県まで北から南まで作られていますが、生産量は鹿児島県がダントツの第1位になります。そして、第2位が千葉県です。
ソラマメの中でも長莢種(ちょうきょうしゅ)のソラマメは、四国を中心に発達した品種になり、香川県では郷土食材の1つとして自治体でも紹介されています。
良いソラマメの選び方
新鮮なソラマメは、サヤの緑色が鮮やかで艶があるものを選びましょう。
鮮度が落ちているソラマメは、筋などは特に、茶色に変色する部分がでてきます。
サヤはふっくらと膨らんで、弾力のあるものを選んでください。良いソラマメは、持ったときに重みを感じるくらいの物がおすすめです。

さやから取り出した豆だけで売られているものは、傷むのが早いのですぐに使う場合のみ利用しましょう。
ソラマメに含まれる栄養素
豆類であるソラマメは、植物性タンパク質を豊富に含みます。ほかにもビタミンB群、カリウムをはじめとするたくさんのミネラルを含むのが特徴です。
また、ソラマメは完熟の茶色になった豆としての「ソラマメ」と、若さやでの野菜としての「ソラマメ」では、栄養素の量が違ってきます。
生でも乾燥でも葉酸がたくさん
ソラマメは生で食べる若さやのものも、乾燥させた豆として食べるものも葉酸を豊富に含みます。
乾燥させると食物繊維が3倍以上
ソラマメは、生のときよりも、乾燥させたときやお多福豆にすると、生の3倍から3.5倍の食物繊維が含まれます。
カリウムも乾燥させると倍増
たくさんのカリウムを含むソラマメですが、こちらも生の未熟なソラマメよりもたくさん摂ることができるのが、乾燥ソラマメです。
生で摂ろうビタミンC
ビタミンCは、保存や加熱で減少してしまう栄養素です。そのため、乾燥させたソラマメにはビタミンCがほとんど含まれません。
生のソラマメには、ビタミンCも豊富に含まれます。
乾燥したソラマメは、煮豆などに使う薄茶色の豆になりますが、ビタミンC以外では、よりたくさんの栄養を摂ることができます。
特に、生にはあまり含まれないリン、鉄、亜鉛も、乾燥したソラマメには含まれます。
ビタミンCを多く含む野菜としては、他に以下があります。こちらものちほどご覧ください。
ソラマメによる健康効果

カリウムで健康な体つくり
カリウムは、細胞内液でミネラルや水分のバランスを摂る栄養素です。細胞外液のナトリウムと対の関係になっており、塩分過多になりがちの日本人の食事では、なくてはならない栄養素です。
カリウムを摂ることで、ナトリウムの余分な吸収を抑える働きがあります。余分なナトリウムの吸収を防ぐことで、高血圧予防、頻脈・不整脈の予防をすることができます。
また、腎臓の健康にも関わるため、筋肉の脱力感や手足のしびれを予防するなど、健康な体作りにソラマメは役に立ちます。
特に乾燥ソラマメは生のソラマメよりも多く含みますので、煮豆を食べるということはとても大切なことになります。
乾燥ソラマメは貧血予防効果の鉄分も豊富
ソラマメは乾燥させると、鉄分がホウレンソウのおよそ3倍、生のソラマメよりも2倍以上になります。豊富な鉄分は鉄欠乏性貧血の予防に重要な栄養素になります。
貧血予防には、乾燥ソラマメを食べると良いですね。
動脈硬化予防
ソラマメに含まれる葉酸は、細胞の再生、赤血球の形成に必要です。高齢者の認知症予防効果もあると考えられています。
細胞の再生をすることが動脈硬化予防や神経障害、胎児の発育異常を防ぐ効果もあるということで、高齢者だけでなく妊娠中の女性もしっかりと摂りたい野菜です。
ソラマメの下処理と保存方法
ソラマメの下処理
ソラマメは、サヤの中から豆を取り出し、黒い筋の部分に包丁の手もとの角で少し切り込みを入れておきます。すると、茹でたあと皮がむきやすくなります。
鍋にたくさんの水と、水1リットルに塩大さじ1強を入れて沸騰させた湯に入れ、1分半茹でます。茹で上がったらすぐザルにあげます。
冷水に入れる人もいますが、栄養素の流出を防ぐためにも、うちわなどで仰いで冷ましたほうが、ほくほくした食感を保つこともできます。
ソラマメの保存方法
生のソラマメは、乾燥しないようにポリ袋などに入れて、冷蔵庫の野菜室で保存します。 冷凍保存するときは、サヤから出し、塩茹でしたものを冷凍しましょう。
茹で時間は1分ほどにし、温かいままバットなどに並べて、つかないようにして冷凍庫へ入れます。凍ってから、ポリ袋に入れて保存します。
ソラマメのおすすめの調理法

乾燥させたソラマメは、煮豆のほかに炊き込みご飯などにも利用できます。
簡単にできるソラマメの一品料理「ソラマメとエビの炒め物」をご紹介します。
ソラマメとエビの炒め物の材料 (2人分)
| 食材 | 分量 |
|---|---|
| ソラマメ (サヤつき) | 500g |
| むきエビ | 10尾 |
| 塩黒コショウ | 少々 |
| ニンニク | 1カケ |
| オリーブオイル | 大さじ2 |
ソラマメとエビの炒め物の作り方
-
たっぷりの水に塩大さじ1から1.5を入れて沸騰させます。
-
ニンニクはみじん切りにします。ソラマメはさやから出して、切り込みを入れておきます。
-
沸騰したお湯にソラマメを入れて2分茹でます。ざるに上げて水気を切り薄皮をむきます。
-
フライパンにオリーブオイルとニンニクを入れ、中火でニンニクの香りがたつまで炒めたら、エビを入れます。
-
エビの色が変わったら、ソラマメを入れて油が全体に馴染むまで炒めて、塩と黒コショウで味を整えます。
まとめ
春から夏に楽しめる野菜のソラマメと、乾燥させて煮豆として楽しめるソラマメ。ソラマメは1つで2度楽しむことができます。
それぞれの栄養を理解し、食感を楽しんで、料理のレパートリーを増やしてみましょう。