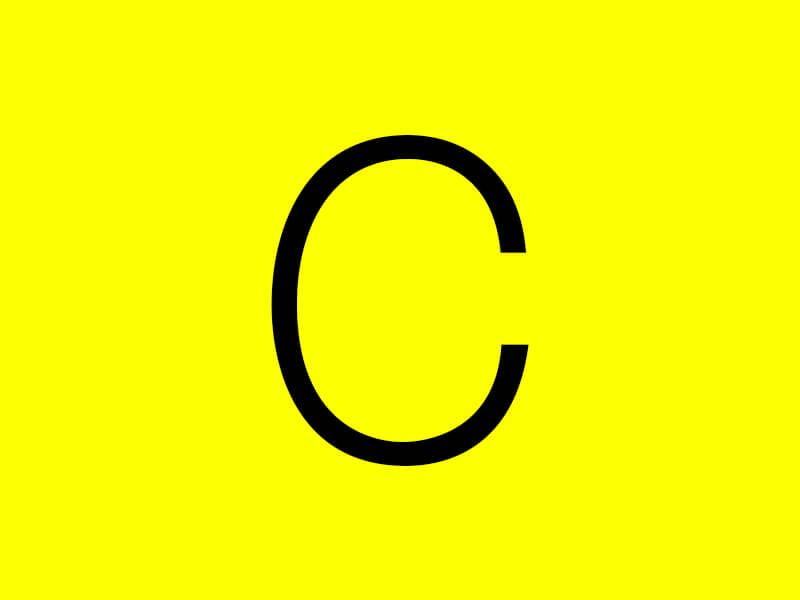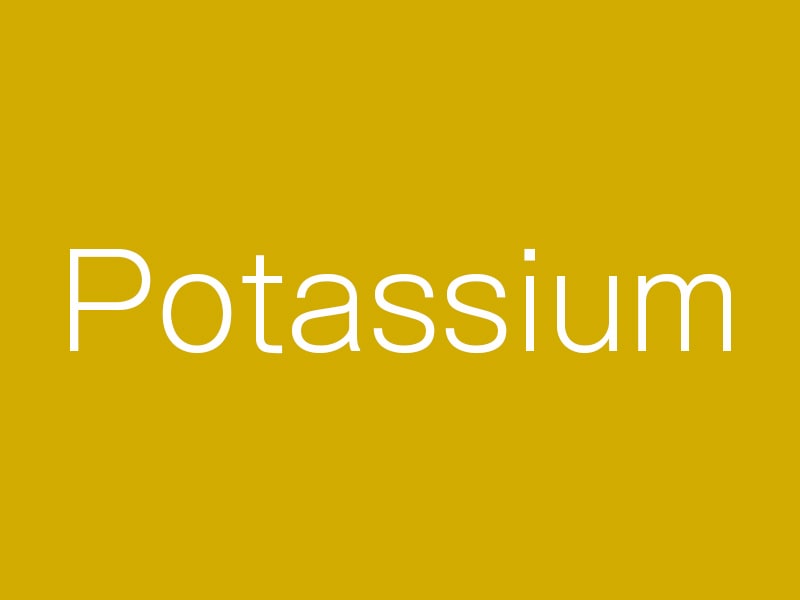サヤエンドウ、キヌサヤ、サヤインゲンと似たような言葉があり、いったいどれがどれかわからない、という方もいるのではないでしょうか。
マメ科エンドウ属のサヤエンドウは、別名「キヌサヤ」とも言います。サヤエンドウと絹さやは同じものになります。
サヤエンドウは、細長く平たくなったサヤの中に小さな緑の豆が入っています。一方でサヤインゲンは、丸く細長い筒状のサヤになっていて、中は細長い白っぽい豆が入っています。名前は似ていますが、違う野菜になります。
そんなサヤエンドウの栄養と効能について見ていきましょう。
スポンサーリンク
サヤエンドウの起源と歴史
サヤエンドウは、エンドウがまだ熟していないサヤを食用とするときの呼び名です。
実エンドウが熟していない状態で豆として利用するのが「実エンドウ」と呼ばれ、それが「グリーンピース」になります。
最近、人気のスプラウト「豆苗」はエンドウの若芽になるため、豆苗、サヤエンドウ、グリーンピース、エンドウ豆はまさに同じ野菜が成長する姿を楽しめる出世野菜といえますね。
サヤエンドウの原産地は、地中海沿岸地域、中央アジアから中近東となっています。その歴史は古く、紀元前より存在したツタンカーメンの墓地からも出土しています。古代ローマ帝国やギリシャでも栽培されていた、と考えられています。
日本には、インドから中国、そして8世紀~10世紀ごろに伝来されたという伝えもありますが、実際に食された記録があるのは江戸時代に入ってからとされています。
栽培当初は、マメ科の穀物として利用されていましたが、13世紀に入り若いサヤを利用するようになります。これがグリーンピースを食する始まりです。
明治時代、欧米から良い品種が導入されると、日本でも全国的に普及されるようになります。
サヤエンドウの種類
サヤエンドウには、若くまだ実として未熟なものから、実が大きくなったもの、熟したものと色々な成長に従って、名前も食べ方も違ってきます。
サヤエンドウ (絹さや)

エンドウ豆の若サヤを食用とするものをサヤエンドウといいます。その中でも小型の主要品種を絹サヤといいます。
サヤが薄く、手でつかむと衣ずれのような音がするものが良いため「キヌサヤ」とも呼ばれます。
大型絹さや
普通のサヤエンドウと違い、10cm以上になります。日本には昭和初期にカナダから輸入されました。
「オランダサヤ」「フランスサヤ」などの品種があり、関西や九州で多く栽培されています。
スナップエンドウ (スナックエンドウ)

実が熟してもサヤも豆も柔らかいため、サヤごと食べることができます。
しかし、サヤエンドウのようなハギレの良さはありません。
スナップエンドウについては以下にまとめていますので、後ほどご覧ください。
グリーンピース

エンドウの未熟な種子を食すもので、爽やかな香りと独特の風味を味わうことができます。季節感あふれる野菜の1つで、生は春から初夏にかけての時期に出回ります。
料理の彩りのほか、スープやサラダ、炊き込みご飯など様々な料理に利用することができます。
砂糖エンドウ

砂糖エンドウ、または砂糖サヤと呼ばれています。絹さやに比べると豆がふっくらして見えます。
皮はスナックエンドウよりも薄く、甘みを感じる糖度が高めで、食べると甘さを感じることができるのが特徴です。
サヤの表面からでも、豆のふくらみをしっかりと見ることができます。
ツタンカーメンのエンドウマメ

普通のサヤエンドウと違い、濃い紫色のサヤを持つエンドウ豆です。
古代エジプトのツタンカーメン王の墓の中から発見された、豆の子孫と言われるところから「ツタンカーメンのエンドウマメ」と呼ばれています。
日本にはアメリカから1956年頃に伝わり、古代エジプトに関係しているエンドウ豆として、主に学校などの教育機関で知られています。
サヤエンドウの食感
サヤが薄くて、サヤも実も食べることができるのがサヤエンドウです。
シャキシャキと歯触りがよく、炒めるときでも煮物でも、このシャキシャキ感を残すことが美味しく食べるためには重要になります。
サヤエンドウの旬と有名な産地
年間を通して出回っていますが、一番の旬は3月になります。
東京で出回っているのは、愛知県・鹿児島県・長崎県が産地のものになります。東京でサヤエンドウを食べることができるのは10月から6月までになり、真夏は輸入のサヤエンドウになります。
全国的に最も収穫量が高いのは鹿児島県指宿市で、第2位は和歌山県の印南町になります。
より新鮮なサヤエンドウを食べるときは、春先を選んでください。
良いサヤエンドウの選び方
サヤエンドウは、色が鮮やかでみずみずしい物を選びましょう。薄くても、くにゃくにゃ曲がるものは鮮度が落ちていますので、選ばないようにしましょう。
また、収穫されたときに切り口が茶色くしぼんでしまっているものは、サヤエンドウとして食べるには時間が経ちすぎています。

キヌサヤエンドウの場合は、育ち過ぎていないものを選びます。サヤの上から見て豆が膨らんでいるものは、もう硬くなってしまっています。
柔らかいサヤを食べますので、サヤがみずみずしく、濃い緑色をしているものをおすすめします。
サヤエンドウに含まれる栄養素
たくさんのビタミン
サヤエンドウには、ビタミンC、ビタミンE、β-カロテンといった、たくさんのビタミン分を含みます。
サヤエンドウに含まれるビタミンCは、エダマメやオクラよりも量が多く含まれています。
ビタミンCは血管を丈夫にして内出血を予防する効果があります。また、抵抗力を高める働きがあり、風邪やインフルエンザを予防する働きもあります。
ほかにも、体内でビタミンAに代わる、β-カロテンを豊富に含みます。
ビタミンCやβ-カロテンを多く含む野菜としては、他に以下があります。
食物繊維
サヤエンドウは豆ですが、野菜の面も持ち、食物繊維を多く含みます。
サヤエンドウがグリーンピースになると、さらに食物繊維が増えます。
カリウムとモリブデン
サヤエンドウには、カリウムやモリブデンといったミネラルも多く含みます。
カリウムはナトリウムとバランスを取って、ナトリウムの余分な吸収を抑える働きがあります。
さらに、モリブデンは体内で鉄分の利用を促す作用があります。そのため、モリブデンを摂ることで貧血予防が期待できます。
尿素や脂質・糖質の代謝にも必要なミネラルになります。
カリウムを多く含む野菜としては、他に以下があります。
サヤエンドウによる健康効果

ビタミンCで風邪予防
サヤエンドウにたくさん含まれるビタミンCは、血管を丈夫にして抵抗力を高める働きがあります。傷の治りを早くしたり、風邪にかかりにくい丈夫な体を作ります。
また、不足すると口内炎などを引き起こすビタミンB2や葉酸も含み、口内炎を早く治すビタミンCも多く含むため、サヤエンドウは口内炎予防と早期治癒効果があります。
風邪予防についてはヒントを以下にまとめてみましたので、併せてご覧ください。
カリウムで味噌汁でも高血圧予防
味噌汁は塩分を含みますが、近年高血圧の方でも1日2杯までなら食べても健康効果があることが分かってきました。
その中でも、カリウムをたくさん含む具材を使うと、さらにナトリウムの吸収を予防する効果があります。
そこで、カリウムを含むサヤエンドウは、味噌汁の具や炒飯、野菜炒めなどの塩味の料理のときに利用すると、高血圧予防効果があると考えられています。
高血圧予防についてはヒントを以下にまとめてみましたので、併せてご覧ください。
食品添加物の解毒効果
サヤエンドウに入っているモリブデンは、尿酸という、最終老廃物を作り出すときに不可欠な酵素の働きを助ける働きがあります。
肝臓や腎臓に含まれるミネラルで、様々な食品に含まれる食品添加物を解毒する効果があります。
食品添加物の解毒作用があるモリブデンを摂ることで、発がん物質の吸収を予防する働きもあると考えられ、期待されています。
食物繊維でダイエット
サヤエンドウは、食物繊維をたくさん含みます。
食物繊維は腸内環境を整え、余分な脂質や糖質の吸収を抑えます。さらに、サヤエンドウは糖質や脂質が少ないため、ダイエットに最適な食材と言えます。
ダイエットについてはヒントを以下にまとめてみましたので、併せてご覧ください。
サヤエンドウの下処理と保存方法
サヤエンドウの下処理
サヤエンドウは、食べるときに筋を取って調理をします。
サヤエンドウの筋はへたの部分をもち、そのまま下の方向にゆっくりと引っ張ります。すると、綺麗に先端まで筋が取れます。
同じように反対側の筋も取り、下処理をします。
調理をする時は、塩を入れた熱湯で軽く茹でることで、シャキシャキとした食感を残したまま楽しむことができます。
煮物や味噌汁、炒めものに入れるときも、先に入れて火を通すのではなく、できるだけ火から下ろす1分前に入れるようにしましょう。
また、ちらし寿司や肉じゃがに入れるときは、別茹でして混ぜることで、食感を残したまま美味しく食べることができます。
サヤエンドウの保存方法
サヤエンドウを保存するときは、キッチンペーパーなどに包み、さらにビニール袋に入れて口を閉じ、冷蔵保存をしましょう。
サヤエンドウは、しっかりと密封することで冷蔵で1週間ほど保存することができます。
さらに保存をしたいときは、筋を取りサッと1分弱ほど茹でて水気を切り、ジッパー付きの袋に入れて空気を抜き、冷凍保存しましょう。
使う時はそのままレンジでチンしたり、熱湯をかけて使うことができてとても便利です。
サヤエンドウのおすすめの調理法

サヤエンドウは、その色とシャキシャキの食感を楽しむことができます。
色と食感を活かした調理、サヤエンドウの炒め物をご紹介しましょう。
サヤエンドウの炒め物の材料 (4人分)
サヤエンドウの炒め物の作り方
-
サヤエンドウは筋を取ります。ネギは斜めの薄切りにします。
-
フライパンにオリーブオイルを熱して、ナガネギを炒めしんなりしたら、サヤエンドウを加えて炒めます。
-
サヤエンドウの色が鮮やかになったら、汁を切ったツナをほぐしながら加えて、酒を加えひと混ぜします。
-
醤油とショウガのしぼり汁を加えて炒め合わせ、器に盛り付けます。好みでコショウをふります。
ショウガとツナ、長ネギとサヤエンドウの炒めものは、さっぱりとしていて副菜にもおつまみにもピッタリです。
サヤエンドウと言えば、味噌汁の具にしたり、イカや鶏肉と炒めたり、八宝菜の具にしたりといったところが、定番の調理法です。
少し面白いレシピでは、サヤエンドウとスナップエンドウ、サヤインゲンを軽く茹でて、スライスしたオニオンと一緒に柚子の香りのポン酢で和える、エンドウ&インゲンの和え物といったものもあります。
簡単にできますので、ぜひ作ってみてください。
まとめ
身近な野菜のサヤエンドウですが、まだまだ知らないことがたくさんありますね。
真夏は国産のサヤエンドウが手に入りにくくなりますが、ぜひ冬は鍋で、そして春先はちらし寿司で、サヤエンドウを楽しんでみましょう。