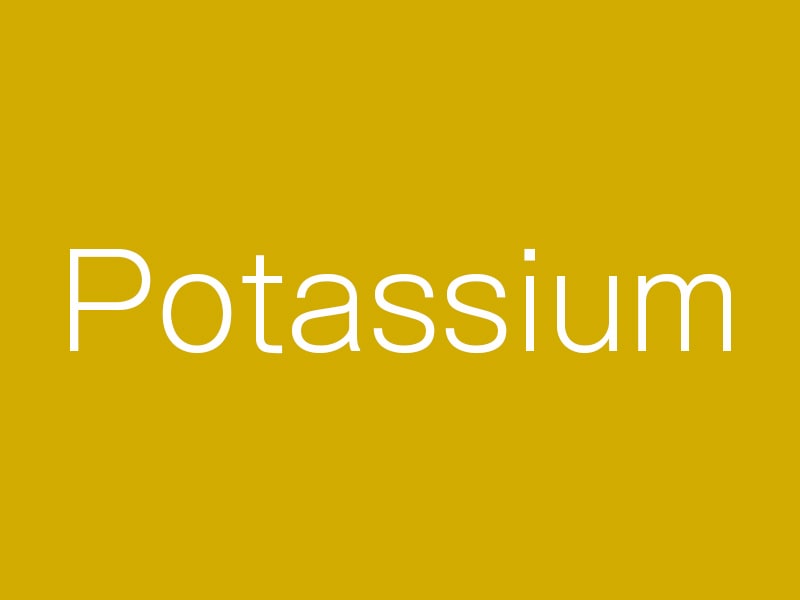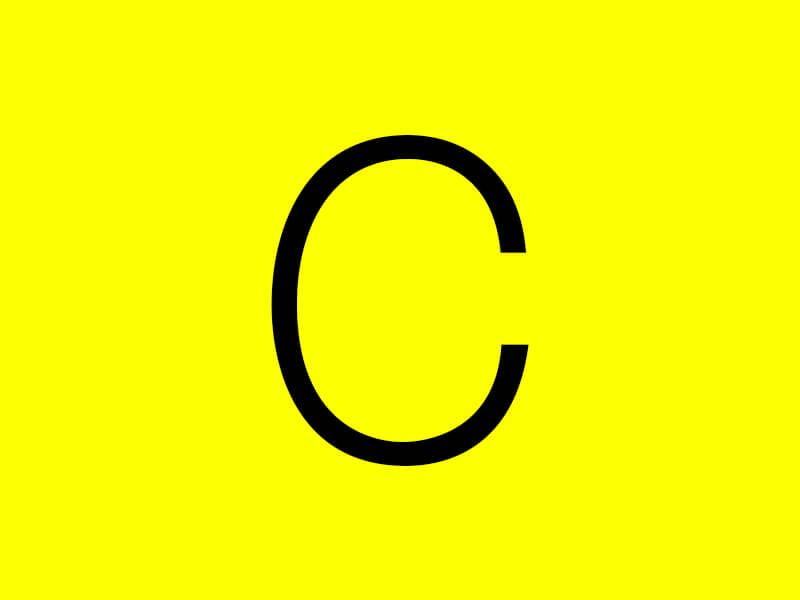マメ科マメ目のモヤシは、太陽の光がなくても育ちます。白くて細身の人を「もやしっ子」と呼びますが、見かけよりも栄養素が高く、お財布にも優しい野菜です。
そんなモヤシの栄養と健康効果、歴史をまとめました。
スポンサーリンク
モヤシの起源と歴史
中近東地方、東部地中海地方沿岸から東方イラク地方、トルキスタン地方を経由し、中国から広がったと考えられていますが、いつ、どのように日本へ伝来したかは、正確にはわかっていません。
日本での栽培の歴史は、350年から400年ほど前に遡ります。東北や九州の農家を中心に栽培されていましたが、大正時代には都市部にも広く普及しました。戦時中には、貴重なビタミンCの供給源として重宝されていたようです。
モヤシの種類
モヤシは種子が発芽してできる野菜です。日本での主なモヤシの種類としては、緑豆、ブラックマッペ、大豆から生産されている3種類のモヤシが挙げられます。
国内で消費されるモヤシの9割が緑豆由来で、特徴はやや太めで癖のない味。もやしの味わいとシャキシャキとした歯ごたえを残しやすく、モヤシだけでも料理に存在感を持たせることができるので人気があります。
ブラックマッペから生産されるモヤシは緑豆のものと比べると、細くほんのりと甘みがあります。大豆から作られるモヤシは、豆が付いたまま出荷され、独特の食感があり、ナムルやスープに使用されます。
その他、ブロッコリースプラウトやトウミョウ、カイワレダイコン、レッドキャベツ、アルファルファなども、実はもやしの仲間です。
モヤシの旬と有名な産地
季節を問わず、一年中栽培することができるため、旬の時期は存在しません。
ただし、温泉モヤシとして有名な青森県の大鰐温泉モヤシの収穫時期は11月から4月下旬になります。
良いモヤシの選び方
茎が淡黄色か純白であり、ひげ根の先までみずみずしいものが良いでしょう。

茎が黄褐色のものや、ひげ根の先が茶色いものは古くなっている証拠です。
モヤシに含まれる栄養素
タンパク質やカリウム、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンCといったビタミン類、そして食物繊維やカルシウムなどを含みます。
低カロリーで、豆の状態よりも消化が良いのも特徴です。
モヤシによる健康効果
ダイエット効果
モヤシのカロリーは、100gで約14kcal。
モヤシは種子に栄養があるだけではなく、発芽し、成長をする過程で種子が持つ以外の栄養素を作ることができる野菜です。栄養は豊富でありながら低カロリーであるため、ダイエットの成果につながりやすくなります。
ダイエットについてはヒントを以下にまとめてみましたので、併せてご覧ください。
血圧を下げる効果
モヤシに含まれるカリウムは心臓機能や筋肉機能の働きを調整し、血圧を下げる効果が期待されます。
カリウムが多く含まれる野菜は、以下があります。
高血圧予防についてはヒントを以下にまとめてみましたので、併せてご覧ください。
病気の予防
ビタミンCもモヤシに含まれる栄養素のひとつですが、鉄分の吸収を促したり血管を強くしたりする働きがあります。
がんや動脈硬化、風邪といった病気の予防が期待され、コレステロール値を下げるのに一役買ってくれるでしょう。
ビタミンCが多く含まれる野菜は、以下があります。
もし風邪にかかってしまった際に、早く治すためのヒントを以下にまとめてみました。こちらも併せてご覧ください。
モヤシの下処理と保存方法
モヤシの下処理
新鮮なものは、生で食べることもできます。下処理をしなくても問題ありませんが、芽とひげ根を取ると、舌触りも良く、美味しく食べることができます。
モヤシは無菌状態で出荷されますので、調理前にしっかり洗う必要はありません。洗いすぎると、水溶性であるビタミンCは水に溶けて、流れてしまいます。
モヤシの保存方法
痛みやすい食材ですので、購入した日に使い切ることが一番です。使い切れなかった場合はポリ袋などに入れて、冷蔵庫で保存をしましょう。
モヤシのおすすめの調理法
ビタミン類は熱に弱いため、過度な加熱は避けたほうが良いでしょう。炒め物を作る際は、最後にモヤシを入れて、熱を通す程度にしたほうが、ビタミン類を壊さずに摂ることができます。
おすすめの調理法は、蒸すことです。ゆでたり炒めたりするよりも、蒸した方が栄養素が壊れにくく、ビタミンCが流れ出ることも最小限に食い止めることができます。
電子レンジを使って蒸せば、少量の水で、しかも短い時間で調理ができるので、比較的栄養素を壊しづらい調理法といえます。
モヤシと豚肉の蒸し物は、熱が均一に通るよう、モヤシと豚バラのスライスを耐熱皿の上で平たく並べ、電子レンジで加熱するだけでできます。簡単で、栄養素を比較的保つことができるレシピです。