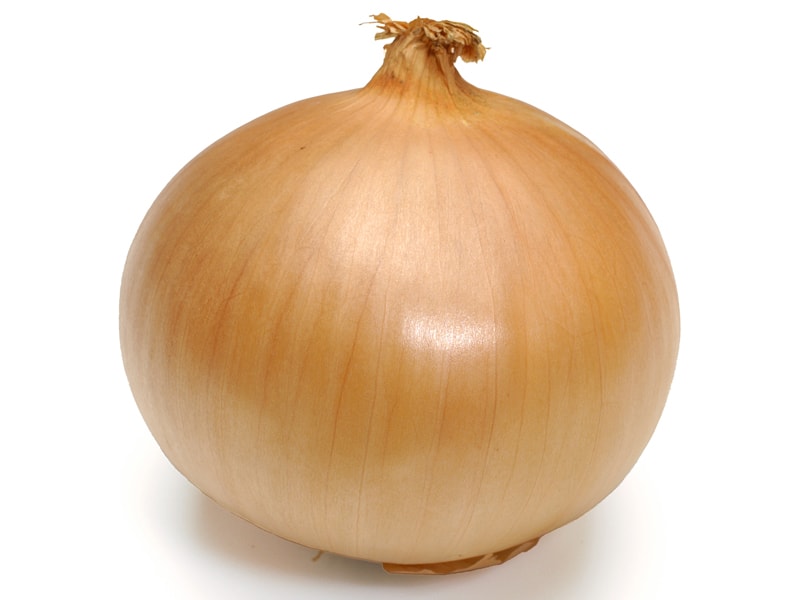ナス科ナス目のトマトは、何にでも使える万能野菜!生でも加熱調理しても食べられる野菜です。様々な形や大きさがあり、赤い色が特徴です。
彩りが欲しい食卓で活躍します。
そんなトマトの栄養と健康効果、歴史をまとめました。
スポンサーリンク
トマトの起源
トマトは、インカ帝国で栽培されていたのが始まりです。スペイン人によってヨーロッパにもたらさましたが、当初のトマトは観賞用でした。
イタリアで19世紀に食用として品種改良され、その後アメリカに伝わりました。
日本へは、1708年に伝来したという説があります。江戸時代には「赤ナス」と呼ばれ、やはり観賞のために生産されていました。食用として普及したのは、戦後になってからです。
トマトの種類
日本では約120もの種類が確認されています。1玉が150g以上のものを大玉トマト、40gから150gまでのものを中玉トマト、40g以下のものを小玉トマトといいます。
大玉トマトの品種で有名なものは「桃太郎トマト」。1玉が200gから230gもあり、皮が硬く、崩れにくいという特徴があります。こちらはスーパーなどで目にしたり、おいしいと実感されている方も多いことでしょう。
中玉トマトで多く流通しているものが「フルティカ」。酸味が少なく、糖度が7%から8%あります。皮が薄く、果肉が柔らかいので、生のままでも食べやすいのが魅力です。
小玉のトマトの大半を占める品種が「千果」です。真ん丸でつやがあり、糖度が8%から10%あります。
トマトの食感
トマトは、皮と実と種で異なる食感を持ち合わせている野菜です。新鮮なものの皮はパリッと張りがあり、実はしゃりしゃりして厚みがあります。
そして種はプチプチとして水分が多めです。
トマトの旬と有名な産地
ビニールハウスでの栽培も盛んなため、一年中出荷されますが、旬は7月から8月になります。
北海道、茨城、千葉、愛知、熊本など日本全国で栽培されています。
良いトマトの選び方
光沢があり、よく色づいているものを選びましょう。

形が三角や五角になっているものは、中が空洞になっていることが多いので、全体が丸みを帯びて、重いものが良いでしょう。実が硬くしまっていて、ヘタが張ったものが質の良い証拠です。
しおれていたり、黄ばんでいるもの、黒く縮んでいるものは、鮮度が落ちているので注意しましょう。
トマトに含まれる栄養素
β-カロテン、グルタミン酸、ミネラル、ビタミンC、ビタミンA、リコピン、ケルセチン、カリウムなど多くの栄養素が含まれています。
「〇〇が赤くなれば、医者が青くなる」と言えばリンゴですが、リンゴと並んでトマトにも同じようなことが言えます。トマトもリンゴと同じように、栄養豊富な健康野菜であることに由来しています。
トマトによる健康効果
アンチエイジング効果
トマトに豊富に含まれるリコピンは、抗酸化作用があります。シミやシワの予防などのスキンケア効果や、肌の老化を防ぐ効果があります。
アンチエイジング効果を持つ野菜は、他に以下があります。
血管の病気の予防
トマトの皮部分には、ケセルチンという成分が多く含まれています。ケセルチンには、血管を強化する働きがあります。この働きは、動脈硬化など血管の病気を予防する効果につながっています。
動脈硬化など生活習慣病予防の効果を持つ野菜は、他に以下があります。
むくみの解消と血圧上昇の抑制効果
カリウムは、体内にある余分な塩分や水分の排出を促します。これにより、水分によるむくみの解消につながりやすくなったり、血圧が上がりすぎることを抑えられるといわれています。
むくみ解消についてはヒントを以下にまとめてみましたので、併せてご覧ください。
高血圧予防についてはヒントを以下にまとめてみましたので、併せてご覧ください。
むくみ解消の効果を持つ野菜は、他に以下があります。
トマトの下処理と保存方法
トマトの下処理
生で食べることが一般的なので、きちんと水で汚れを洗い流しましょう。
皮が硬いものや、加熱してから使用する場合は、皮をむくと調理がしやすいでしょう。
トマトの保存方法
保存をするには、袋に入れて冷蔵庫へ入れましょう。適温は5度。かなり日持ちします。
トマトのおすすめの調理法
抗酸化作用のあるリコピンは、生の状態からはあまり摂ることができません。同じ量を摂取した場合でも、生トマトよりも加工品の方が2倍から3倍の吸収率があるとされています。
またリコピンは熱に強く、油を使用した調理方法でも吸収性が高くなります。効率的に摂るためには、トマト缶を使用してパスタソースを作ったり、ミネストローネなどのスープにしたりするのも良いでしょう。