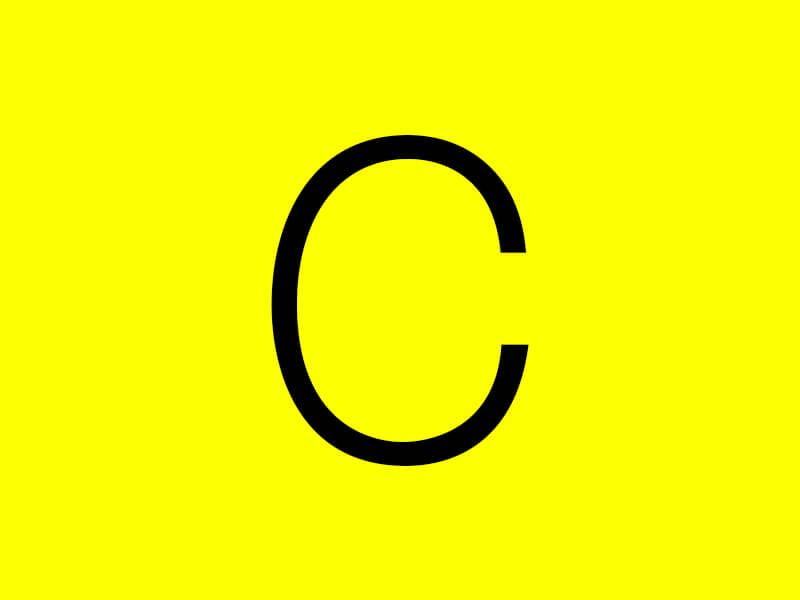ヒガンバナ科キジカクシ目のギョウジャニンニクは、強いニンニク臭を放つのが特徴です。ギョウジャニンニクと呼ばれる葉は、ネギ属の多年草です。
網状繊維の鱗茎を地下に持ち、種子のほかにも不定芽でも増殖します。
しかし、生育速度が遅く、種まきから収穫までの生育期間が5年から7年かかるため、簡単に収穫することができません。
また、群生する場所が国立公園などの自然保護区とあり、流通が少ない希少な山菜です。市場流通量が少ないため、高値で取引されることもあります。
そんなギョウジャニンニクの栄養と効能について見ていきましょう。
スポンサーリンク
ギョウジャニンニクの起源と歴史
日本では北海道や奈良県に多く、近畿地方よりも北側の針葉樹林、混合樹林帯の多い亜高山地帯の水湿地に群生しています。
ヨーロッパ産の基本亜種となるビクトリアリス亜種のギョウジャニンニクは、ヨーロッパの多くの高山に群生しています。
ロシアやモンゴル、アルプス山脈などで多く見られるほか、中国大陸やインドにも群生は広がっています。
1990年から、北海道や日本海側の雪の多い地域で園芸栽培が行われています。
ギョウジャニンニクは種を蒔いてから8年~10年、株を分けてから5年~6年と長い年月がかかります。そのため、品種改良によるギョウジャナという新たな植物の研究もされています。
ギョウジャニンニクの種類
ギョウジャニンニクと、ギョウジャニンニクに類する植物の種類を紹介します。
ギョウジャニンニク (行者大蒜)

ギョウジャニンニクはネギ属ですが、植物としての分類ではユリ科の多年草になります。
スズランに似ていますが、スズランは葉に毒があるため、間違って採取しないよう注意することが必要です。
ギョウジャニンニクの根は、普通のニンニクより香りが強いのが特徴です。臭い防止のために、根の切り口を空気に触れないよう水につけておきましょう。
家庭では、調理前にサッと茹でて水にさらしておきます。
ニンニク

ギョウジャニンニクと同じ、ネギ属の植物になります。
肉の臭み消しや、料理に食欲をそそる香味を与えるニンニクは、香味野菜の代表的な野菜です。
「ニンニクの芽」と呼ばれている茎の部分は、炒め物などに使われることが多いです。
また、球根は香辛料や薬味として使用されています。
ギョウジャナ(行者菜)

宇都宮大学農学部の開発で、ギョウジャニンニクとニラを交配し、新たに生まれた植物です。
外見はニラに近くなりますが、茎の太さはギョウジャニンニクと似ています。
ニラと同じように1年で収穫することが可能なため、2008年から山形県で本格的な栽培と販売が開始されました。
ノビル

ヒガンバナ科ネギ亜科ネギ属の多年草です。食用として利用されますが、生のネギのように辛いところから「ヒル」の名前がつきました。
葉はまっすぐの線状のものが20cm~30cmの長さで数本出てきます。雑草に紛れて生育するため、花茎が伸びてきて初めて気が付くことが多い植物です。
根は小さな球形で、小さなタマネギのようになります。
ギョウジャニンニクの食感と香り
ギョウジャニンニクはサッと茹でると、ニラのようなシャキシャキとした食感になります。
加熱しすぎた場合には、ホウレンソウのように柔らかい葉を味わうことができます。
茎には、ニンニクと同じ味や香りがあります。独特な香りがありクセになる方もいますが、食べすぎるとニンニクよりも臭いが口の中に残ります。口臭にならないように注意しましょう。
ギョウジャニンニクの旬と有名な産地
ギョウジャニンニクの旬は、ハウス栽培のものが1月~3月、天然のものは3月~5月になります。北海道南部では6月まで最盛期が続く場所もあります。
一般的に国内では、北海道や東北地方、奈良県に多く、近畿地方よりも北側の針葉樹林、混合樹林帯の多い亜高山地帯に自生するとされています。
しかし、市場に出回っているものはほとんど北海道産です。北海道では昔から「アイヌネギ」と呼ばれ、天然物が出荷されています。
岩手県など東北地方でも栽培がおこなわれておりますが、東日本震災のあと、東北地方ではイノシシの被害(食べないが土を掘り起こされてしまった)により、また一からの栽培になっています。
良いギョウジャニンニクの選び方
ギョウジャニンニクは、葉が開くと香りが薄くなっていきます。むしろソフトな香りに変わりますので、株のみずみずしさで選びましょう。
株がしっかりとしているものは問題がありません。

新鮮なものは、葉の先までピンとなっていて、みずみずしくハリがあるものになります。根元の切り口が新しいものを選びましょう。
古くなると切り口が溶けたような、柔らかい感じになります。
ギョウジャニンニクに含まれる栄養素
ギョウジャニンニクが希少で高値の野菜でありながらも、重宝されるのはその栄養素の高さです。
健康に良いといわれるニンニクを超える、ギョウジャニンニクの栄養素をご紹介しましょう。
ニンニクよりも多く含まれるアリシン
ギョウジャニンニクの栄養素で最も目を見張るものが、アリシンです。
ニンニクよりも多く含まれるアリシンは、ギョウジャニンニクを切ったり刻んだりと細胞を壊すことで作られます。
豊富なβ-カロテン
ギョウジャニンニクには、大量のβ-カロテンも含まれます。
色の濃い葉野菜に多いβ-カロテンですが、その量はトマトやピーマンの5倍になります。
β-カロテンが豊富なその他の野菜については、以下にまとめています。
免疫力を高めるビタミンC
ギョウジャニンニクは、ビタミンCも豊富で、その量はシソの葉の2倍、ダイコンの4倍にもなります。
免疫力を高めるビタミンCは、風邪予防効果もあります。血管を丈夫にするため、傷が治りやすくなるという働きもあります。
ビタミンCを多く含む野菜としては、他に以下があります。
ほかにもビタミンKや食物繊維を多く含む反面、脂肪やカロリーが少ない、健康とダイエットにおすすめの食材です。
ギョウジャニンニクによる健康効果

ギョウジャニンニクのアリシンで高血圧予防
ギョウジャニンニクに含まれるアリシンは、強い抗菌・抗カビ作用を持つ物質です。
血糖値や血液中のコレステロール値を抑え、高血圧や糖尿病などの予防や、改善のための効果があります。血液をサラサラにすることで、血栓や心筋梗塞、脳梗塞を予防します。
調理すると速やかに分解されるアリシンは、動脈硬化に対抗する助けとして医学的にも用いられています。
活性酸素の発生を抑え、動脈硬化などの生活習慣病を予防する効果もあります。
強い殺菌作用で食中毒予防
ギョウジャニンニクに含まれるアリシンには、生で摂ることで強力な殺菌作用を発揮します。
アリシンの殺菌作用は食中毒のほか、結核菌やブドウ球菌・赤痢菌・チフス菌などの病原菌から守る効果があるといわれています。
しかしその殺菌効果の強さから、腸内細菌の善玉菌に対する殺菌作用もあり、胃腸障害を起こすこともあります。摂りすぎには注意をしましょう。
疲労回復効果
アリシンは、ビタミンB1の働きを高める効果があります。
豚肉に含まれるビタミンB1は、ご飯などの糖質をエネルギーにする際に必要な補酵素です。
ビタミンB1を多く含む食品と一緒に摂ることで、疲労回復や滋養強壮効果もあるといわれています。
疲労回復についてはヒントを以下にまとめてみましたので、併せてご覧ください。
抵抗力を高め、がんの予防にも効果
ギョウジャニンニクに含まれるビタミンCやビタミンEには、酸化防止剤作用があります。アリシンには、免疫力を高める働きもあります。
ビタミンCは免疫力や抵抗力を高めるだけでなく、血管を丈夫にして血行促進にもつながり、様々な病気に対する抵抗力を付けます。
そのため、がんの予防にも効果があると言われています。
血行促進は冷え性や動脈効果、血栓の予防、老化防止にも効果的です。
ギョウジャニンニクの下処理と保存方法
ギョウジャニンニクは、根元を乾燥させないことが大切です。湿らせたキッチンペーパーで根元をくるみ、袋に入れて冷蔵庫に立たせて保存します。
冷凍で保存するときは、サッと熱湯をくぐらせてから冷凍しましょう。
使うときは、凍ったまま刻んでそのまま調理することができます。
醤油漬けで保存
ギョウジャニンニクの一般的な保存方法は、ギョウジャニンニクを丸ごと、または適当な長さに切ったものを、サッと熱湯にくぐらせます。
その後、すぐに冷水にとり水気を拭きます。
よく水気をふき取ったら蓋つきの密封容器などに入れて、醤油をギョウジャニンニクが完全に浸るまでたっぷり注いで密封します。
1年ほどは持ちますが、漬け込み時間によって風味が変化します。食べる時は、刻んでご飯に乗せてそのまま味わうことができます。
ギョウジャニンニクのおすすめの調理法

ギョウジャニンニクはそのままサッと茹でて和え物にする食べ方と、豚肉などと一緒に調理することで、より栄養効果を高める調理法とがあります。
定番の和え物「ギョウジャニンニクの酢味噌和え」
ギョウジャニンニクの酢味噌和えの材料 (4人分)
| 食材 | 分量 |
|---|---|
| ギョウジャニンニク | 100g |
| だし入り味噌 | 大さじ2 |
| 豚ひき肉 | 200g |
| 酢 | 大さじ1 |
| 砂糖 | 大さじ1 |
| 顆粒だし | 大さじ1 |
| 一味唐辛子 | お好み |
| かつお節 | 適量 |
ギョウジャニンニクの酢味噌和えの作り方
-
ギョウジャニンニクはサッと洗ったら、たっぷりの熱湯で茹でます。茹で上がりは1分ほど、色が鮮やかになったところでザルに上げます。
-
ザルに上げたら、流水でしめます。
-
調味料を混ぜます。
-
茹で上がったギョウジャニンニクと、調味料をあえて小鉢に盛り付けます。
-
上からかつお節、お好みで一味唐辛子を添えます。
簡単なお酒やご飯のお供になります。
栄養満点!「ギョウジャニンニクと豚バラ肉の炒めもの」
ギョウジャニンニクと豚バラ肉の炒めものの材料 (2人分)
| 食材 | 分量 |
|---|---|
| ギョウジャニンニク | 100g |
| 豚バラ肉 | 150g |
| シメジ | 1束 |
| 塩 | 少々 |
| コショウ | 少々 |
| 醤油 | 小さじ1 |
| ごま油 | 小さじ1 |
| 鷹の爪 | 1つ |
ギョウジャニンニクと豚バラ肉の炒めものの作り方
-
ギョウジャニンニクの根元の赤い部分を手ですっと下にひいて、取り除きます。汚れている部分を流水で洗い、3cm~4cmにカットします。
-
しめじは根をカットし、食べやすい大きさに分けておきます。長いものはカットします。豚バラ肉も、大きさによって同じくらいの大きさにカットしておきましょう。
-
フライパンを中火で熱し、ごま油を敷いて切った豚バラ肉を炒めます。
-
火が通ったらシメジとギョウジャニンニクを入れ、塩・コショウで味付けして最後に醤油をまわし入れます。
-
全体に火が通ったら出来上がりです。臭いが残りますので外出をしない休日前がおすすめです。
まとめ
山菜の中でも希少なギョウジャニンニク。希少で健康に良い、と聞くと手に入れたくなった方もいるのではないでしょうか。
あまり暑い地域向きではありませんが、ギョウジャニンニクの苗を販売しているところもあります。
なかなか手に入らない希少な野菜ですが、ご興味を持った方はぜひ、自家製ギョウジャニンニクを栽培してみてはいかがでしょうか。