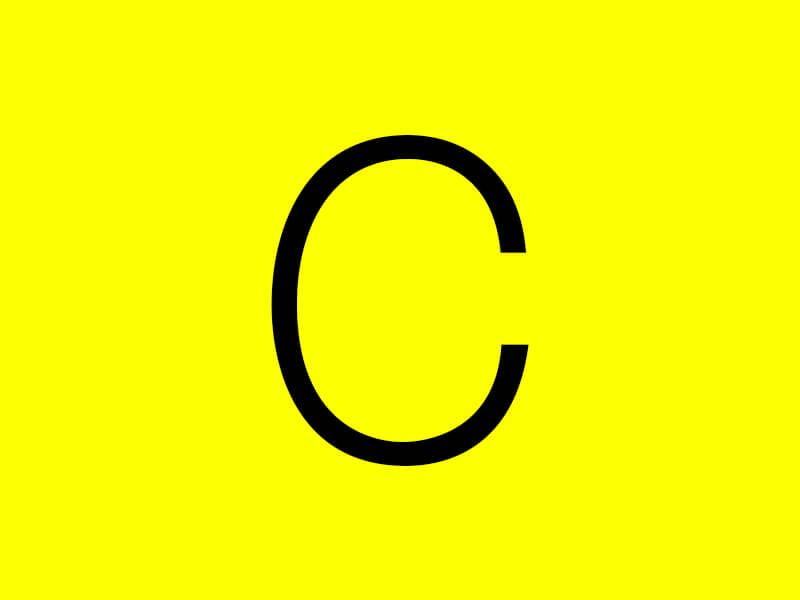キャベツはアブラナ科アブラナ属の多年草の野菜で、1年を通して出荷されます。生食でも加熱してもおいしい野菜で、和・洋・中様々な料理で使うことができる野菜の1つです。
そんなキャベツの栄養と健康効果、歴史をまとめました。
スポンサーリンク
キャベツの起源
キャベツの原産地は、ヨーロッパの地中海や大西洋の沿岸と言われています。紀元前600年ごろには、すでにケルト人が栽培方法をヨーロッパの各地に伝えていたようです。
そのころのキャベツは今のような球のような形をしておらず、現在のキャベツの形になったのは約1000年前と言われています。
日本にキャベツが伝わったのは江戸末期で、その後、戦後の食生活の洋食化とともに日本全国に普及しました。
キャベツの種類
キャベツには春に出回る春キャベツと、冬キャベツがあります。
「春キャベツ」はみずみずしく、生食用としては最適です。「冬キャベツ」は冬の寒さに耐えて、ずっしりと巻きが固くなっています。葉がしっかりとしているので、加熱しても煮崩れず甘みが増します。

他にも、小玉で丸く葉が柔らかい「グリーンボール」、紫色で肉厚の「紫キャベツ」、葉の付け根の脇芽である小さい「芽キャベツ」などがあります。
キャベツの旬と産地
春になると、柔らかくおいしい春キャベツを味わうことができます。
冬の間の産地として有名なのは、愛知、神奈川、千葉などの温かい地方です。夏から秋にかけては、北海道や群馬の嬬恋、長野の野辺山などの涼しい地方の高原キャベツが多く出回ります。
良いキャベツの選び方
ハリとつやがあり、切り口が白いキャベツが新鮮です。切り口が変色したり乾燥したりするものは古くなっていますから、避けてください。

春キャベツの場合は巻きがゆったりしていて軽いものを、冬キャベツは巻きがしっかりしていてずっしりと重いものを選ぶと良いでしょう。
キャベツに含まれる栄養素
キャベツに含まれる豊富な栄養素として特徴的なのが、ビタミンUです。あまり聞きなれない栄養素ですね。ビタミンUは胃腸の粘膜を修復し、胃潰瘍や十二指腸潰瘍の予防に効果が期待できます。別名「キャベジン」とも呼ばれるビタミンです。
胃腸の粘膜を正常に保つ効果がある他の野菜は、以下が挙げられます。
また、キャベツにはビタミンCも豊富です。紫キャベツにはポリフェノールの一種、アントシアニンが豊富に含まれており、視力回復効果や老化の原因となる活性酵素の除去効果が期待できます。
キャベツ同様、ビタミンCが豊富な野菜としては、以下が挙げられます。
その他ビタミンCを多く含む野菜としては、他に以下があります。
キャベツによる健康効果
キャベツに含まれるビタミンCは、美容効果の高いビタミンです。美肌効果が期待できますし、疲労回復や抗ストレス効果もあります。また、キャベツ100gあたりのカロリーはたったの23kcalですから、たくさん食べてもカロリーは気になりません。
しかも、キャベツに含まれる食物繊維が水分を吸収することでお腹の中で膨らみ、満腹感を得ることができます。さらに、食物繊維を得ることで、便通も促してくれます。
キャベツは美容に欠かせない野菜と言えそうですね。
疲労回復についてはヒントを以下にまとめてみましたので、併せてご覧ください。
ダイエットについてはヒントを以下にまとめてみましたので、併せてご覧ください。
便秘解消についてはヒントを以下にまとめてみましたので、併せてご覧ください。
キャベツのおすすめ調理法とは?
キャベツと言えば、回鍋肉などの炒め料理やとんかつなどの揚げ物の付け合わせにピッタリの食材です。そんなキャベツの栄養素を壊さず上手に調理するためには、どうしたらよいのでしょうか。
キャベツを調理する上で気を付けたい点
まず気を付けたい点は、ビタミンCやビタミンUは水溶性のビタミンであるということ。だから、水につけすぎると、キャベツに含まれているビタミンがどんどん逃げてしまいます。
キャベツを洗う時は、サッと洗って水につけすぎないのが良いようです。
キャベツに含まれるビタミン類を効果的に摂取するための調理方法とは
まず、生で食べる方法。これは、熱に弱いビタミンCを壊さずに摂取することができる方法です。ただ、生だとたくさん食べることは難しいですよね。そこで、キャベツを蒸すことで、カサが減り柔らかくなって食べやすくなります。
ただし、蒸しすぎるとビタミン類が溶けだしてしまいますから、1分~2分くらいの短時間だけ蒸すようにすると、ビタミンを効率よく吸収できます。
炒めるとビタミンCは減ってしまいますが、カロテンは油と相性が良いので効率よく吸収することができます。