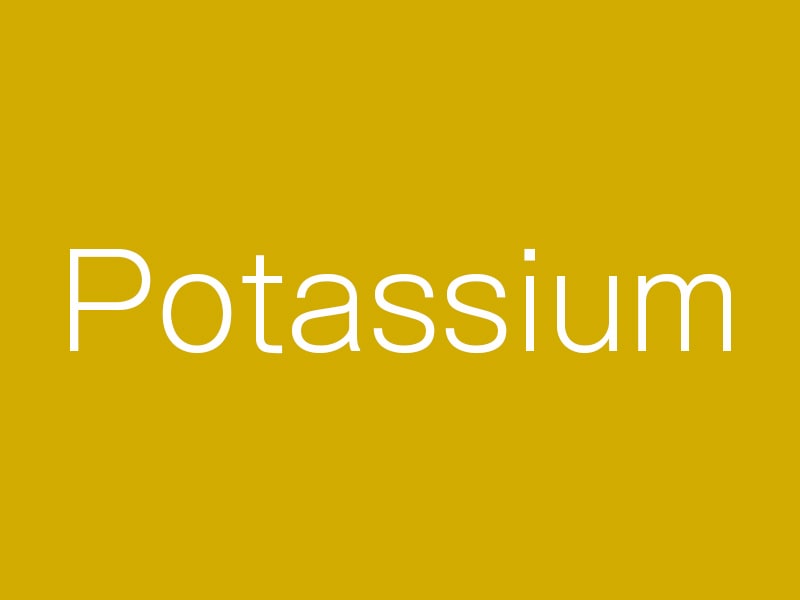ウドは、ウコギ科タラノキ属の多年草で山菜として有名な野菜の1つです。若葉・つぼみ・芽および茎の部分が食用となり、根を乾燥させたものは漢方としても使用されています。
そんなウドの栄養と健康効果、歴史をまとめました。
スポンサーリンク
ウドの起源と種類
ウドは独特の香りがあり、シャキッとした歯触りが特徴の山菜です。日本原産の野菜で、軟化栽培は江戸時代に始まったとされています。
ウドには緑色の「山ウド」と白色の「軟白ウド」があります。
山ウドは、日当たりの良い場所か半日陰の傾斜地などに自生している天然のもののことを指します。(中には栽培したものもあります)
軟白ウドは日の当たらない地下などで栽培されているもので、スーパーなど市場に出回っているウドはこれを指します。全国的に栽培されていますが、軟白ウドは東京の「東京ウド」、大阪の「三島ウド」が特産品として有名です。
また、ウドは出荷時期によっても呼び名が異なります。11月~2月に出荷されるものを「寒ウド」、3月~5月に出荷されるものを「春ウド」と言い、春ウドの方が軟らかく香りも良いです。
ウドの旬と有名な産地
天然のウドは収穫できる時期が短く、南の方から収穫が始まり、3月~5月にかけて全国的に収穫されますが、栽培しているものは通年流通されています。
群馬県や栃木県で多く生産されています。
良いウドの選び方
山ウドは、太さが均一で短いもので香りが強いものを。軟白ウドは、白くて太くまっすぐ伸びており、全体的にうぶ毛があるものを選ぶようにしましょう。

ウドに含まれる栄養素と効果・効能
ウドの成分のほとんどが水分であるため、栄養価が高い野菜ではありません。
しかし、その中でもカリウムや食物繊維を豊富に含んでおり、低カロリーのためダイエット食品にもぴったりです。
カリウム
カリウムは、血圧上昇の原因となっているナトリウムを体の外へ排出する働きがあるため、高血圧や動脈硬化などの予防に有効であると言われています。
高血圧予防についてはヒントを以下にまとめてみましたので、併せてご覧ください。
食物繊維は水溶性よりも不溶性の量が多く、整腸作用があり便秘改善などに効果があります。
便秘解消についてはヒントを以下にまとめてみましたので、併せてご覧ください。
カリウムが多く含まれる野菜は、他に以下があります。
ポリフェノール
苦味(アク)はポリフェノールの一種であるクロロゲン酸で、抗酸化作用があり、細胞のダメージを防いでくれます。
ただし、アク抜きの際に水に溶け出てしまうため、摂取量の確保はあまり期待できません。
ウドの保存方法
軽く濡らした新聞紙に包んで冷蔵庫(野菜室)で保存し、3日~4日で使い切るようにしましょう。
日に当たると硬くなり、時間が経つと苦味が増してしまいます。
ウドのおすすめの調理法
特に山ウドはアクが強いため、アク抜きが必要です。酢水にさらしたり、茹でてアクを抜きましょう。
天ぷら
山菜の一種ということもあり、葉や先端を天ぷらにすることで香り良く食べることができます。
サラダ
ウドは生で食べることができますので、シャキッとした食感を楽しんでください。ただし、時間が経つにつれアクが強くなるため、アク抜きは必須です。
炒め物、煮物、和え物
他にも、炒め物や煮物、和え物など様々な調理方法で食べることができます。特に酢味噌との相性が良いため、酢味噌和えがおすすめです。
また、軟白ウドは皮まで食べることが出来、捨てる部分がないと言われています。皮はきんぴらにすると美味しいです。
ウドのおすすめレシピ
ウドは漢方でどう使われている?
根を乾燥させたものを「独活(ドクカツ)」と言います。微温性で辛く苦い味がします。
発汗・鎮痛・解毒・抗潰瘍・血管収縮作用を持つため、風邪・頭痛・リウマチ・冷え性などに効果があります。
「荊防敗毒散」「独活葛根湯」「独活寄生湯」「独活湯」などに使用されています。
まとめ
山菜のひとつであるウドは、普段はあまり食べることのない野菜かもしれません。しかし、低カロリーのためダイエット食品にも適しており、整腸作用、血管系疾患にも効果があります。
栽培方法や収穫時期により特徴が異なるため、様々な調理方法で楽しんでみてはいかがでしょうか。