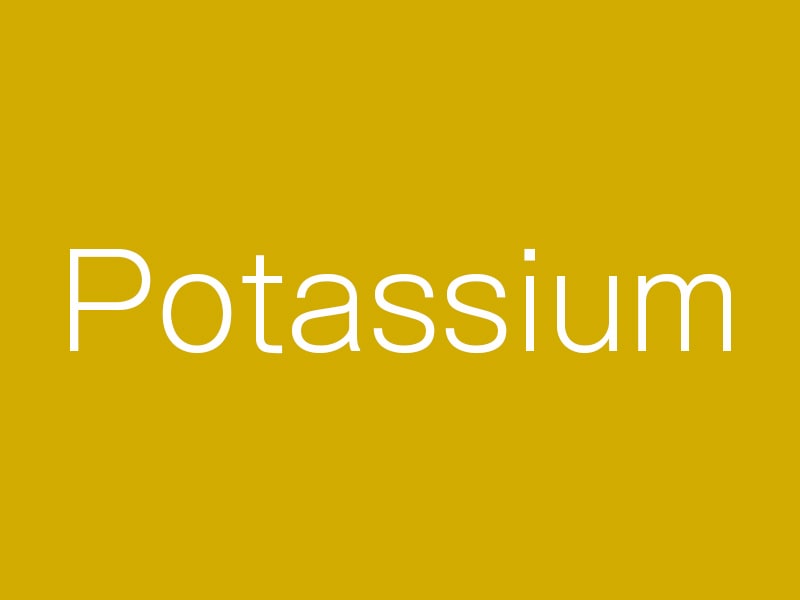ヒラタケ科ヒラタケ属のヒラタケは、大きいものだと一株で10キロにもなると言われています。和食にも洋食にも中華にも合う、おいしいキノコです。
そんなヒラタケの栄養と健康効果、歴史をまとめました。
スポンサーリンク
ヒラタケの起源
ヒラタケは、古くから日本でも食べられてきました。平安時代には「今昔物語」に登場し、毒キノコをヒラタケと偽って食べさせる話があります。
その後の時代にも、様々な文献に登場することから、日本人に親しまれてきたキノコと言えます。
かつては、「ホンシメジ」「シメジ」などとして売られることが多かったヒラタケですが、最近はきちんと「ヒラタケ」と表記されるようになりました。
欧米では、カサが開いた形が牡蠣に似ているため、」「オイスター・マッシュルーム」と呼ばれています。
ヒラタケの種類
一般に流通しているものは、おがくずなどで栽培する菌床栽培のヒラタケです。カサが平らで、香りと歯ごたえが良いです。天然ものや原木栽培のヒラタケもあります。

ヒラタケより色が薄くカサが少し小さい「ウスヒラタケ」は、歯ごたえがあって香り良く、クセが少ないのが特徴です。
ヒラタケの旬と産地
大量生産が可能な菌床栽培もののヒラタケは、一年中出回ります。天然ものの旬は秋で、寒い時期に採れたヒラタケを「寒茸(カンタケ)」と呼ぶ地域もあります。
主な産地は、新潟県や長野県、静岡県です。
良いヒラタケの選び方
良いヒラタケはカサが肉厚でピンと張っており、軸がしっかりしています。

痛みがあったり変色したりしているものは、鮮度が落ちていますから避けましょう。
ヒラタケに含まれる栄養素
ヒラタケには、ビタミンB群やナイアシン、パントテン酸、食物繊維、カリウム、葉酸などの栄養素が含まれています。
ヒラタケによる健康効果
血流を良くして生活習慣病や冷え性を予防
ヒラタケに含まれるナイアシンには、血液の流れを良くする効果が期待できます。そのため、動脈硬化や脳梗塞などの生活習慣病を予防する効果が期待できます。
また血流が良くなると、冷え性が改善します。
冷え性改善についてはヒントを以下にまとめてみましたので、併せてご覧ください。
ナイアシンを含む野菜は、ヒラタケの他に以下があります。
疲労回復
ヒラタケに含まれるビタミンB1は、糖質の代謝を促す働きがあり、効率良くエネルギーを作り出すことができるようになります。
そのため、疲労回復に役立ちます。
疲労回復についてはヒントを以下にまとめてみましたので、併せてご覧ください。
皮膚や粘膜を健康に維持し、風邪予防
ヒラタケに含まれるビタミンB2には、皮膚や鼻、のどの粘膜を維持し、成長させる働きがあります。
皮膚や粘膜が強くなると、風邪などのウィルスに強くなります。
もし風邪になってしまった場合の早期回復については、ヒントを以下にまとめてみましたので併せてご覧ください。
脂肪の代謝を良くする
ヒラタケのパントテン酸は、加熱されても壊れにくい性質があります。パントテン酸は、脂肪を代謝する力を高めるために必要不可欠な栄養素です。
腸内環境を改善し便秘解消
ヒラタケには、不溶性食物繊維のβグルカンが豊富に含まれています。
不溶性食物繊維は水分と一緒に摂ると、腸の老廃物や有害物質を吸着して体の外に排出してくれます。そのため腸内環境が改善し、便秘解消の効果を得られます。
便秘解消についてはヒントを以下にまとめてみましたので、併せてご覧ください。
むくみと高血圧の予防
ヒラタケに含まれるカリウムには、体の中のナトリウム(塩分)を、余分な水分と一緒に排出してくれる働きがあります。
体の塩分濃度が適切に保たれるため、高血圧を予防する効果が期待できますし、余分な水分が排出されることでむくみの予防にもなります。
高血圧予防についてはヒントを以下にまとめてみましたので、併せてご覧ください。
むくみの解消についてはヒントを以下にまとめてみましたので、併せてご覧ください。
カリウムが含まれる他の野菜については、以下にまとめましたので、併せてご覧ください。
葉酸で貧血予防
葉酸は新しい赤血球を作り出すために必要不可欠なビタミンですから、ヒラタケで葉酸を補えば貧血の予防になります。
また、妊娠すると体内の葉酸は不足しますし、胎児の先天性障害が起こるリスクが高まります。妊娠中は、ヒラタケやホウレンソウなどを積極的に摂って葉酸を補給しましょう。
※厚生労働省によると、1日に摂取できる葉酸の上限は、1000μg(1mg)までとしています。摂り過ぎには充分注意してください。
ヒラタケのおすすめ調理法
ヒラタケは、鍋に入れたり味噌汁の具にしたり、天ぷらや炊き込みご飯にするのもお勧めです。
また、和食だけでなく、洋食にも合います。オリーブオイルとの相性が良いので、ソテーにしたりパスタの具にしたりするのも良いでしょう。