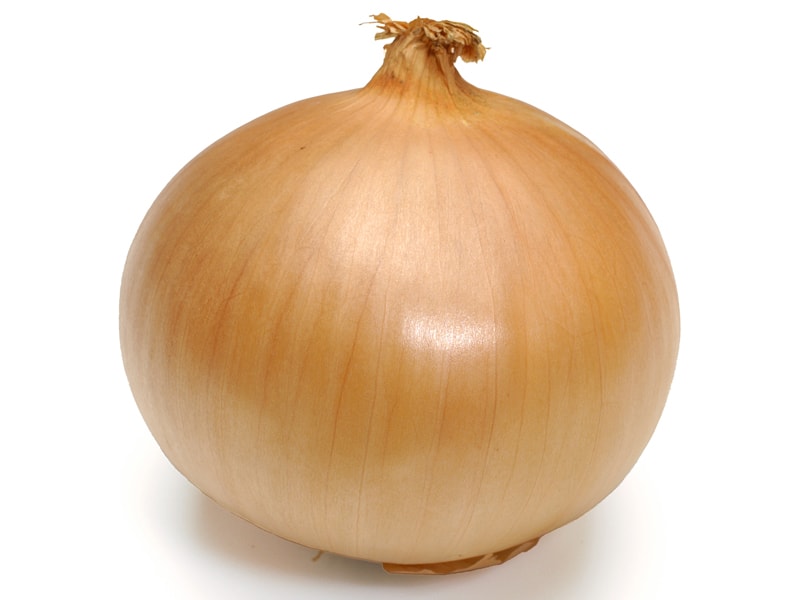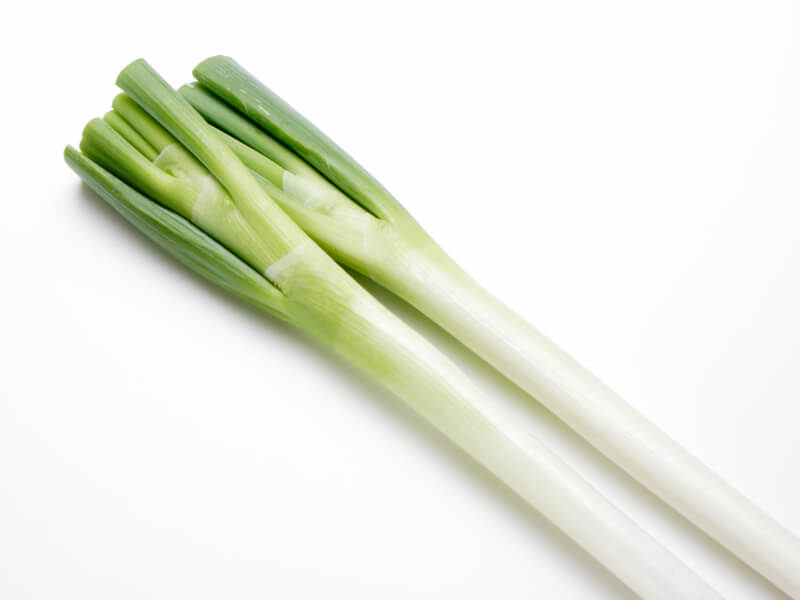日常の家事に追い立てられて、冷蔵庫に野菜を入れっぱなしにしてしまう―。
食べられるか不安になってそのまま捨ててしまうか、勇気を出して食べるか、いつも選択を迫られます。
野菜に限らず、ほとんどの食料には賞味期限や消費期限があります。日ごろ忙しいと、日持ちする野菜ばかり買ってしまい、すぐに腐ってしまうような野菜は買いにくくなってしまうでしょう。
少しでも野菜の賞味期限を延ばすには、保存方法がとても重要。気を付ければ毎日の食卓に野菜の種類が増えるかもしれません。
スポンサーリンク
野菜に賞味期限は明記されていない
カップラーメンやお菓子などには、当たり前のように書かれている賞味期限や消費期限。生鮮野菜に書かれていることは多くありません。
実は、生鮮食品にはこれらの期限を表示する義務がありません。反対に、加工食品には表示義務があります。
では、野菜の賞味期限はどれくらいなのか、と聞かれると、それぞれの野菜の状態を見て判断される方がほとんどでしょう。変なにおいがしたり、変色したり、芽が生えたり、すぐに感じ取ることができる変化なら分かりやすいですよね。
もちろん、これらは野菜の可食を見極めるために重要な要素です。しかし、「少し黒ずんでいる」とか「ちょっとしおれている」くらいなら食べられる野菜も多く存在します。
ここからは、野菜の賞味期限の目安や食べてはいけない状態について見ていきましょう。家庭でよく使う野菜の保存方法もあわせて紹介しますので、参考にしてみてください。
野菜ごとの賞味期限とおすすめの保存方法
ジャガイモ

カレーに肉じゃが、ポテトフライに炒め物。八面六臂の家庭の味方。ジャガイモは野菜の中でも特に保存が利くことで有名です。
そんなジャガイモの可食状態の見極めは、「芽が出ているか否か」「皮が緑色に変色しているかどうか」によります。芽と緑色の皮のどちらにも、ソラニンという毒素が含まれているからで、摂取してしまうと嘔吐などの食中毒に襲われます。
芽が出ているのは一目見ればわかるのですが、変色しているかどうかには注意が必要です。あまりに時間が経っていて、明らかに緑色に覆われたものならば食べてしまう心配はありませんが、一部分だけが変色していることも珍しくありません。
特に家庭で量を使うときに、1個ずつ確認しない場合もあるでしょう。とはいえ、注意さえしていれば取り除くのは簡単です。緑に変色している部分を取り除けばそのまま食べることができます。
この時、外側から緑色の皮を剥いただけで安心せず、ちゃんとジャガイモの身の中まで見るようにしてください。緑色になっている身も取り払ったほうが良いでしょう。
保存のポイント
ジャガイモの保存には冷暗所が適しています。特に暗い場所が望ましいのはこの変色を防ぐため。光に当たるとジャガイモが光合成を行い、結果としてソラニンが発生してしまいます。
また、乾燥した保存状態が好ましいので、保存の際には湿気をふき取り、風通しの良い光の当たらない場所に置いておきましょう。土がついているならそれも除去してください。乾燥剤代わりに新聞紙で包むなどの工夫をしても良いでしょう。
確かにジャガイモは比較的長期保存が可能ですが、それを過信せず、定期的な消費を心がけておくことをおすすめします。
キャベツ

キャベツは時間経過で変化がありますので、傷み方を見るのは難しくありません。
少し変色していたり、葉が萎びている程度ならば問題ありません。気になるならば該当する部分を取り除くなどして食べましょう。
特に食べられない状態と判断されるのは、広範囲が黒くなってしまっていたり、汁やぬめり、異臭が確認されるときです。これらは腐っている状態で、さらに進むと溶けて崩れていきます。
保存のポイント
キャベツを保存する場合は、まずは芯をくりぬいてください。芯を取り除くとキャベツの成長が止まりますので、傷み方が遅くなります。
キャベツの保存は冷蔵保存です。最適な温度は0度~5度のため、冷蔵庫に入れておきましょう。軽く水気をふき取るくらいでOKですので、タオルや新聞紙で巻いた後、ポリ袋に入れて保存します。
キャベツはジャガイモと違って乾燥させてはいけませんので、このようにして常に湿気がある状態にします。
冷蔵庫で保存しているからと言って腐らないわけではありませんので、油断は禁物です。特に袋に入れて保存するので、中が見えません。なるべく気を配っておきましょう。
モヤシ

賞味期限が短い野菜として知られるモヤシ。安くて使い道も多いので便利ですが、まとめ買いしにくいために、かゆいところに手が届かない感じです。
モヤシの腐敗のサインは、以下の通りです。
- 芽が変色している
- 水がたまっている
- しなびている
- 柔らかくなっている
- 溶けている
- 異臭がする
この中でも特に、芽の変色や水の発生は、比較的よく目にするのではないでしょうか。
少しくらいならば芽の変色や水の発生まで確認できても食べることはできます。その場合でも、もちろん加熱は必須です。
しかし、水が大量に溜まった状態や、モヤシ全体が変色してしまった状態は危険信号です。異臭や柔らかさの確認もしつつ、廃棄してしまったほうが安全でしょう。
保存のポイント
気になる保存方法ですが、水に浸ける方法があります。
生の状態で水に浸し、密封して冷蔵庫で保存します。保存中は毎日水を取り替えられれば理想的でしょう。最大1週間程度の賞味期限になります。
もっと長く保存したいという方は、冷凍保存がおすすめです。袋から取り出して洗い、水を切ったうえで冷凍保存。
この方法では2週間から3週間の保存が可能ですが、味が変わってしまいますので料理を工夫して対策しましょう。
タマネギ

タマネギの保存と聞いて思い浮かぶのは、ネットに入れて吊るして保存している状態です。実はこのイメージ通りの保存でおおむね問題はありません。
紀元前、古代エジプト王朝時代には労働者に配給されていたとされるタマネギ。逸話が示す通り、賞味期限が長い、使い勝手の良い野菜です。
数か月間の保存が可能とされるタマネギですが、腐ってしまうと、異臭、発芽、変色、軟化などの症状が確認できます。いずれもわかりやすいので、判断に困ることはないでしょう。
ただし、タマネギの中身は層のような構造になっているため、表層が腐っているだけならばそこを取り除けば食べることができます。
また、真ん中だけ腐っている場合もあるため、長期保存したタマネギを使うときは、切って中身を確かめたほうが良いでしょう。
保存のポイント
肝心の保存方法ですが、先述の通りネットやストッキングに入れて吊るすのが理想的です。多くとも5個くらいにして、なるべく小分けにして吊るすようにしましょう。
スライスしたタマネギは、袋で密封して保存します。なるべく空気にさらさないことが重要です。
ナガネギ

ナガネギもタマネギと同じで、軟化が腐敗の兆候です。最終的にはドロドロに溶けてしまいます。当然異臭もセットですので、腐った状態はわかりやすいでしょう。
ナガネギの賞味期限は、目安として1週間。もちろん、そのまま保存するかカットするかで変わってきます。
保存のポイント
ナガネギはそもそも冬が旬の野菜ですので、冷蔵庫が保存に適しています。冬であれば冷暗所での保存も可能です。
また、カットしての保存もおすすめです。ビニール袋にナガネギを入れて、4㎝程度の水を入れて密封。ジッパーのついた袋に入れて、倒れないように冷蔵庫に入れることで、3週間の保存が可能です。ただし、ナガネギを取り出すたびに水を入れ替えるようにしてください。
刻みねぎにしてしまったら、キッチンペーパーをタッパーに敷き詰めて保存しましょう。段々キッチンペーパーが濡れてきますので、その時は新しいものに取り換えてください。賞味期限は最大で2週間ほどです。
キュウリ

サラダにサンドイッチと、スライスするだけで活躍できてしまうキュウリ。そのまま保存できれば、朝・昼・夕に加えてお弁当まで時短できてしまう優れものです。ぜひともスライスした状態で保存したいものですね。
キュウリの腐敗の目印は以下の通りです。
- 異臭
- 柔らかくなっている、ぬめぬめとしている
- カビが生えている
- 茶色や黄色などへの変色
他の野菜と同じく、一目でわかる変化ですので、間違っても食べてしまうということはないでしょう。
ちなみに白く変色することもあるのですが、その場合は水分が抜けているだけなので問題なく食べることができます。
ただしこの状態になると大きく味が落ちるため、生ではなく加工して食べることをおすすめします。
保存のポイント
気になる保存方法ですが、スライスしたキュウリを塩もみし、密閉して野菜室に入れるのがおすすめです。
塩もみは、野菜の賞味期限を延ばす保存方法としてポピュラーですが、キュウリをこの方法で保存すると1週間ほど保存することができます。
もしも塩もみをしたくないのであれば、スライスしたキュウリの断面ニラップをかけ、空気が触れないように野菜室に保存するのが良いでしょう。その場合の賞味期限は2日ほどですので、なるべく早く食べてしまうのがおすすめです。
なお、スライスしていないキュウリであれば、キッチンペーパーとラップでまるごとくるみ、野菜室に立てて保存するのが良いでしょう。5日ほど保存することができます。
ニンジン

ニンジンの腐敗の兆候も、他の野菜と同じく異臭やぬめり、軟化です。カビが生えている場合もわかりやすいですね。
ただし、ジャガイモと同じく傷んだ部分を取り除けば食べることはできますので、傷んできた程度であればよく見て食べるかどうかを決めましょう。
保存のポイント
ニンジンの賞味期限は比較的長いことで知られています。新聞紙やキッチンペーパーでくるみ、キュウリのように立てた状態で野菜室に保存しましょう。葉っぱのついたものであれば、根元から切り落としてから保存します。
常温保存も可能な野菜ですが、特に夏場は油断していると腐らせてしまいます。
野菜室に入れた状態で、2週間から3週間ほど保存することができます。日々の備蓄に役立ってくれそうですね。
ピーマン

ピーマンも例に漏れず、異臭、ぬめり、変色、カビなどが腐敗の合図です。
ピーマンはリンゴと同じようにエチレンガスを出し、追熟をする野菜ですので、黄色や赤色の変色ならば問題ありませんが、茶色への変色はNGサインです。
保存のポイント
保存の際は、1つずつ新聞紙やラップにくるみ、ポリ袋などの保存袋に入れて野菜室に入れましょう。エチレンガスを出すため、1つずつ保存しなければどんどん熟していき、腐敗が進んでしまいます。
冬ならば冷暗所で保存しても問題ありません。賞味期限は1週間から3週間程度です。
もっと長いこと保存したいという方は、冷凍保存がおすすめ。種といワタを取り出し、袋に包んで冷凍庫へ入れましょう。
洗ったあとに水気をふき取るのも、忘れずに行ってください。ピーマンは水に弱い野菜なので、このひと手間が重要です。冷暗所での保存の際も、湿度は気にしておくのが良いでしょう。
この状態で1か月ほど保存できます。なお、下茹でをしておくと変色や変質の抑制につながりますので、ひと手間かけてみてはいかがでしょうか。
ニラ

ニラの賞味期限は短く、1週間も放っておくと異臭や軟化が始まります。そのため何もせず冷蔵保存をしたのでは、4日も経てば食べられなくなってしまいます。
保存のポイント
冷蔵保存で長く持たせたいなら、切って水に浸けてから冷蔵庫に入れましょう。一週間ほどの賞味期限にすることができます。
おすすめなのは冷凍保存。好きな大きさに切ったうえで水気をふき取り、袋に密閉して冷凍します。こうすることで1か月ほど保存することが可能です。
ただし、あくまで長期保存におすすめなのが冷凍保存というだけです。冷蔵保存より味が落ちてしまうので、炒め物などの料理に使うようにして対策しましょう。
野菜の保存方法は多種多様
このように、野菜とひとくちに言っても種類がたくさんあり、また野菜も生きていますので、保存方法はそれぞれ異なります。
野菜も生き物―ということは、その保存方法は応用が利くということでもあります。
例えば、レタスとキャベツの保存方法はほとんど同じなので、今回ご紹介した方法でレタスを保存していただいても構いません。
レタスとキャベツはキク科とアブラナ科でそれぞれ違う植物ではありますが、可食部分については良く似ているため、同じような保存方法で大丈夫です。
野菜は、健康を維持するための毎日の栄養摂取に欠かせない、大事な食料。できたら長く保存し、効率的に使っていきたいですね。