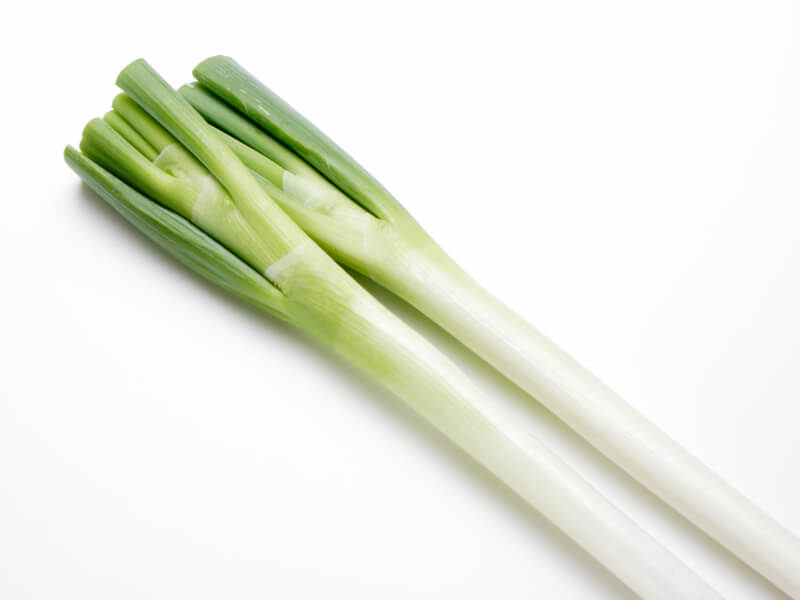吸収率が高く、興味あることにはどんどんやる気が出てくる小学生にとって、野菜の漢字クイズはちょっと違ったアプローチで、その野菜が好きな子も嫌いな子も夢中になれます。
ここでは、小学生が楽しめる野菜クイズについてまとめてみます。
スポンサーリンク
最初は興味が無くとも、正解が続けばやる気につながる

「そんなこと習ってないし、知らないし」が子供の常套句とも言えるセリフですが、人参や大根などよく目にする漢字からスタートして、難易度を上げていき、詰まったところで「でもこれが分かれば物知り博士って言われるかもね」や「自由研究にも使えるよ?」など、誘うことで子供は自信がつき、興味を持ちやすくなると思います。
実際に食べたことのない野菜でも、漢字で想像つくものに興味を持ち「食べてみたい!」となることにもつながり、食育の効果も期待できます。
「赤茄子」は何の野菜か分かるかな?
ナスは読めても、赤茄子は何の野菜のことを示しているのでしょうか?
正解はトマト。江戸時代など外国からやってきた野菜の多くには、その野菜のイメージから付けられた当て字の漢字も多く存在します。
トマトは、初めて見た日本人の「真っ赤な茄子!」という印象から付いた漢字だと言われており、花茄子や唐柿などで表す、複数の漢字を使う野菜もあります。
漢字で野菜当てクイズをやってみよう!
スーパーの売り場で見たことのある簡単な漢字や、一文字でも習った漢字があれば入りやすいですよね。
例えば、下記の漢字が読めるかクイズを出してみましょう。
南瓜
南瓜は「カボチャ」。南蛮から伝わったことが由来。
漢字表記を見たことがある小学生も多いのではないでしょうか。
西瓜
西瓜は「スイカ」。中国にスイカが伝わる際に西からきたのが由来。
南はカボチャ、西もあるねと興味が引けそうです。

竜髭菜
竜髭菜は「アスパラガス」。アスパラガスの葉が龍の髭に似ていることが由来しています。
実際にアスパラガスの葉を見たことがない子もいると思いますが、本当に細くて風になびいているところは髭にそっくりです。
辣薤
辣薤は「ラッキョウ」。辛いニラの意味があります。カレーのお供のひとつですよね。
極小タマネギのような形なので、絵でクイズを出せばちびっ子でも分かります。なお、漢字表記は複数あります。

和蘭芹
和蘭芹は「パセリ」。
パセリはオランダセリと呼ばれており、オランダは和蘭、セリは芹、ということからこの漢字になった由来があります。

芽花椰菜
芽花椰菜は「ブロッコリー 」。漢字四文字というところがお洒落なブロッコリー。
いくつか漢字の表記は存在しますが、花の部分が集合して芽のように見えることからついたとの由来もあります。
陸蓮根
陸蓮根は「オクラ」。英語でもokraと表記・発音します。つまり、オクラは元々英語です。
よくメディアなどでも読めない野菜としてトップ3に入るオクラ。栽培方法も名前も独特です。
いかがでしょうか?調べればたくさん出てくる野菜の漢字、どれもこれも面白いものばかりです。
なんで当て字がほとんどなの?
野菜のほとんどが外国から伝わっているからです。
野菜が伝来した際、漢字に無理矢理はめ込もうとしたところ当て字になったともいわれており、子供だけでなく親の勉強にもなりそうです。
見た目のインパクトやその野菜が何科の植物なのかなど、表現はさまざまで奥深い一面ももっています。
野菜の日本在来野菜と伝統野菜は違う?
日本在来野菜と伝統野菜は別ものです。
日本在来野菜
日本がもともと発祥の野菜。数は20種類ほどしかなく少なめです。主に山菜に多く見られます。
日本の伝統野菜
外国から伝わった野菜を、その土地で独自の改良などを加えて育った野菜。全国調べてみると色々あり、地図方式でクイズをしても楽しいはずです。
クイズで出せる日本在来野菜って何があるの?
日本在来野菜は小さい子や小学生、大人でもちょっと苦手な方がおられるような、山菜系や味も香りも独特な野菜たちのオンパレードです。食べたことも見たことも無い、なんてこともあるのではないでしょうか。
そんなときのクイズは、漢字で書いたカードと、ひらがなもしくはカタカナで書いたカードを組み合わせて正解を導き出すクイズなら高学年向けで良いでしょう。低学年向けには、ひらがなやカタカナの下に絵が入っているとより簡単になると思います。
独活
独活は「ウド」。春に新芽や若い茎を天ぷらなどにして食べたりします。
山芋、自然薯
山芋「ヤマイモ」、自然薯「ジネンジョ」。スーパーで見かける大和芋や長イモ。外国から入ってきて改良されたものですが、それらも山芋と呼びます。
自然薯だけが日本在来野菜で、特徴は出汁で伸ばして、香りも粘りも強めです。
芹
芹は「セリ」。1月に食べる七草粥でも登場する芹は、日本在来野菜の一つです。宮城の芹鍋も有名ですよね。
蕗
蕗は「フキ」。春の訪れを感じる蕗、天ぷらや佃煮などで楽しまれています。
小さくコロンとしたイメージですが、中には2メートルくらいまで育つ種類もあります。
三つ葉
三つ葉は「ミツバ」。
茶碗蒸しの上に飾られていたり、すまし汁に入れたり日本の香草的扱いとしても使える三つ葉。そっと添えられてあると嬉しいですよね。

その独特な香りや味にちょっと苦手な子もいると思いますが、アイディア次第で取り入れてみて、ぜひ旬の時期にクイズしながら食べるきっかけにしてみても良いですね。
茗荷
茗荷は「ミョウガ」。
小さいころ祖母に「茗荷をあまり食べ過ぎるとアホになる」と言われた記憶と、玉ねぎのように剥いてバラバラにして叱られた思い出があり、茗荷を見る度に思い出し笑いします。

ただし、言い伝えの内容からは、釈迦の弟子の「周梨槃特(スリバンドク)」という人物の物忘れが酷く、その彼の墓に生えていた草に名を荷って死んでいった彼にちなんで、茗荷と名付けたそうなので、医学的にも問題なさそうですよね。
世界でも茗荷を好んで食べているのは、日本だけだそうです。面白いですね。
今は習ったことのない漢字でも低学年のころ興味を持っておくと、何かの拍子にその漢字に出会ったとき「この漢字って、この前クイズでみたよ」の一言から会話が生まれるかもしれません。
なかには簡単なものだと覚えて、鼻高々にスーパーで大声出して披露してくれるかもしれません。「じゃあ、ちょっと食べてみようか」と食べるきっかけ作りに、クイズから入ることもできます。
伝統野菜クイズとは?
よく耳にする京野菜。最近では、全国の土地特有の伝統野菜が注目を集めています。なかでも、同じ野菜であっても地域によって変貌をとげた野菜もあります。
日本地図を片手に正解を目指したり、かるた方式、絵柄、県名とあわせて野菜の特徴をクイズで学ぶこともできます。
各伝統野菜のクイズと紹介
まずは「大根」チームなど、種類で読み方クイズから入り、そこから各伝統野菜は、何県と結びつくのかを探すクイズをしてみると、他学年同士組ませても面白いかもしれませんね。
低学年の子が高学年のお兄さん、お姉さんに教わりながら何県かを模索していくのは、とっても良い刺激になるのではないでしょうか。
大根
桜島大根(サクラジマダイコン):鹿児島県。世界最大の大根、通常10kg、大物だと20kgの強者も。
守口大根(モリグチダイコン):岐阜・愛知県。食べる部分が2メートルにもなる世界最長の大根。
聖護院大根(ショウゴインダイコン):京都府。京野菜としても有名な丸い形の大根。
蕪
「スズナ」とも呼ばれ、1月の七草粥でも有名です。大根と一緒で根の部分を主に食べますが、野沢菜のように葉をメインで食べる種類もあります。
最上カブ(モガミカブ):山形県。上部が赤紫色で、とても見た目にも美しい長蕪(ナガカブ)。
聖護院カブ(ショウゴインカブ):京都府。大きさは世界最大。「千枚漬け」は冬の京都名産物。
野沢菜(ノザワナ):長野県。京都から「天王寺かぶら」の種が入り、栽培したのが始まり。野沢菜温泉村に伝わり、特産品でのお漬物が有名。
日野菜(ヒノナ):根の上部があざやかな紅紫色。下部は白く細長い。葉も一緒にお漬物が有名。
葱
関東は白ネギ、関西は葉ネギと主に食べる部分が違うのも面白い葱。もっぱら緑葱が普通だった関西の方が、関東のスーパーでびっくりした事も多いのではないでしょうか、また逆もありますよね。
九条ネギ(クジョウネギ):京都府。白根が短く葉が長いタイプ。
下仁田ネギ(シモニタネギ):群馬県。日本のなかで一番太いネギ。
ちなみに、実際にクイズとして考えた内容を低学年の子が挑戦したところ、時間がかかりました。日本地図を勉強している学年の助けがあれば、盛り上がるのではないでしょうか。
名前や文字では分からなかったけれど、絵を見ると「あー、よくお鍋で食べるよね」や「何だっけー、見たことあるよなー」など、がんばって思い出そうとしてくれます。
生産地別の野菜クイズ
生産地は、社会の地理など、教科書で見たことがあるのではないでしょうか。
例えば、メジャーな野菜のジャガイモは、北海道からはじまり全国でランキングを調べて、円グラフに生産地だけ書いて、何の野菜か当てるクイズにしてみるのも面白いかもしれません。
生産地ランキングで野菜を当てよう
1位は北海道で、全体の約60%。2位は鹿児島県で、全体の約6%。3位は茨城県で、全体の約5%。
さあ、分かったでしょうか?答えは「カボチャ」です。北海道強しですね。
1位は北海道で、全体の約30%。2位は千葉県で、全体の約19%。3位は徳島県で、全体の約8%。
今回はいかがでしょうか?答えは「ニンジン」です。千葉県の生産量の多さに少しびっくりです。
1位は茨城県で、全体の約25%。2位は宮崎県で、全体の約20%。3位は高知県で、全体の約9%。
北海道がトップ3に入らなかった野菜、これは何でしょう?答えは「ピーマン」です。
1位は熊本県で、全体の約17%。2位は北海道で、全体の約8%。3位は茨城県で、全体の約7%。
ご家庭のプランター栽培や、小学校ではひとりずつ鉢植えすることも。これは何でしょう?答えは「トマト」です。
トマトは飛び抜けて割合が多い県はないため、作りやすいのかもしれませんね。熊本県はたしかに「くまモン」のパッケージで記憶にも残っています。
以上、生産地クイズでした。スーパーに行ったとき、パッケージや札をよく見てみて、子供と比べてみるのも楽しいかもしれません。そして、そこから新たな子供たちの野菜チャレンジが待っているかもしれませんね。
まとめ
野菜が好きな子・苦手な子と家庭だけでなく、小学校の給食でも苦労があると思います。どんなことからでも野菜に興味がもてたら、そこから食べてみるチャレンジ精神は出てくるのではないでしょうか。
小学校で野菜を栽培して好きになった子もいるので、簡単なことから始められる漢字クイズや遊びで家族でもできそうな「かるた方式クイズ」など、勉強というイメージが強すぎない食育で野菜のことをもっともっと知ってもらえると幸いです。