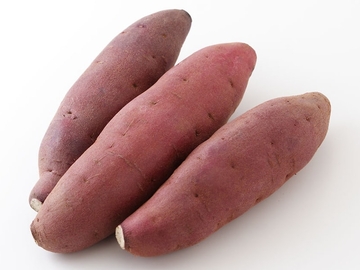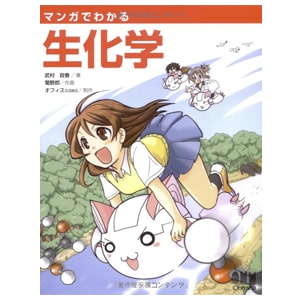脂質が豊富な野菜ベスト10
エダマメ
エダマメは、マメ科ダイズ属の野菜です。大豆が成熟する前に収穫したものをエダマメと呼び、奈良・平安時代から食べられています。栄養豊富で、健康食として世界各国からも注目されている野菜です。
ソラマメ
マメ科のソラマメは、ふっくらとしていながら、ごつごつとしたシルエットが特徴的です。食卓に並ぶと季節を感じる食材でもあります。新鮮なうちに調理して食べることが、美味しくいただけるコツです。
トウモロコシ
イネ科イネ目のトウモロコシは、穀物として私たちの食料や家畜の飼料にもなります。ほかにも、コーンスターチやコーン油として、食材の1つとしても利用されます。世界三大穀物の1つです。
ニンニク
キジカクシ目ヒガンバナ科のニンニクは、ネギの仲間の多年草です。ニンニクはスパイスのイメージがありますが、香味野菜です。その香りの強さから、人と会う前日に食べるのを控えることもあるのでは?
シメジ
シメジにはブナシメジとホンシメジがありますが、実は分類が異なる別物です。私たちが普段口にするのは、ほとんどが人工栽培されたブナシメジです。
マイタケ
マイタケは、サルノコシカケ科マイタケ属で、主に東北地方の栗の木(くりのき)をはじめとする、ブナ科樹木の根元に生えるキノコです。香りが高く、食感が良いため古くから人気の高いキノコです。
モロヘイヤ
モロヘイヤはアオイ科ツナ属の一年生草木です。アラビア語で「王様の野菜」と呼ばれ、その名の通り栄養価の高い野菜です。しかし、実(さや・種)には毒性があるため食べることはできません。
ブロッコリー
アブラナ科アブラナ属のブロッコリーは、木を小さくしたような形をしている野菜です。キャベツの仲間で、野菜類の中でもトップクラスの栄養を持っています。その鮮やかな色合いから、お弁当や洋食によく活用されます。
※数値は100gあたりの含有量です。
脂質とは
1gあたり4kcalをもつ炭水化物やタンパク質に対し、脂質は1gあたり9kcalのエネルギーを生み出すことから、少量で効率の良いエネルギー源となります。
脂質の種類には中性脂肪(トリアシルグリセロール)やリン脂質、ステロイド(コレステロールはステロイドの1種)などがあり、食べ物に含まれている脂質の大部分は中性脂肪です。そのため主に脂質と書かれていれば、この中性脂肪を指すことが多くあります。
また脂質は、脂肪酸を原料に作られており、中性脂肪であればグリセリンに脂肪酸が3つ繋がった構造となっています。そのため、健康維持にはその脂肪酸の質が大切と言われています。
脂肪酸は以下のように飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸の2種類があり、さらに不飽和脂肪酸は一価と多価に分けられます。
| 種類 | 分類 | 含まれている食品 | ||
|---|---|---|---|---|
| 飽和脂肪酸(常温で固体) | 動物性 | バターや肉の脂身など | ||
| 不飽和脂肪酸(常温で液体) | 一価不飽和脂肪酸 | オメガ9系 | 植物性 | オリーブオイル、菜種油など |
| 多価不飽和脂肪酸 | オメガ6系 | 大豆油、ゴマ油など | ||
| オメガ3系 | 魚油・植物性 | サバやイワシなどの青魚、アマニ油など | ||
飽和脂肪酸は体の中で固まりやすい性質があり、量を多く摂りすぎると、血液ドロドロの状態になりやすくなります。
体内での働き
エネルギーが高いことからダイエットの天敵とも扱われやすい脂質ですが、私たちの体では細胞膜やホルモンの構成成分として活躍するという重要な役割を持っています。
また、皮下脂肪は体温維持や内臓を保護する働きもあります。
その他、油で溶けやすい脂溶性ビタミンであるビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンKの吸収を高めてくれます。
多く含まれる食材
調理用油(ゴマ油、菜種油、バターやラードなど)、ナッツ類、お菓子(スナック、ケーキなど)のほか、脂質の多い肉や魚などが主な供給源となります。
野菜ではラッカセイやエダマメが高いですが、100g中、脂質が100%の調理用油(菜種油など)には及びません。果物ではアボカドに多く含まれています。
野菜における脂質
野菜は脂質などのエネルギー源になる栄養素が少なく、水分が多いため、野菜(特に生野菜)ばかりでは体を冷やす原因になることがあります。
また、サラダの具材に緑黄色野菜(ニンジンなど)が含まれていれば、ドレッシングをかけることで脂溶性ビタミン(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK)の吸収アップに繋がります。
1日の摂取量目安
「日本人の食事摂取基準(2015年版)」では、成人で1日に必要なエネルギーのうち20%~30%を脂質から摂ると良いとされています。
例えば1日に摂取するエネルギーを2,000kcalとして考えると400kcal~600kcalに相当し、1日に45g~67gの脂質の摂取を推奨としています。
実際の食生活で考えると、お肉などの食材にも油が含まれていることを念頭に、1日の調理用油の摂取目安量は、成人で15g(大さじ1杯半)程度を適量とされると良いでしょう。
脂質が少ないと便が硬くなるため、便秘になったり、肌が乾燥しやすくなったりと健康や美容面に問題が出てきます。
過剰で代謝しきれなかった脂肪は体脂肪として蓄積され、肥満や生活習慣病の原因につながります。
参考文献

-
改訂新版 いちばん詳しくて、わかりやすい! 栄養の教科書

-
健康診断が楽しみになる! コレステロール・中性脂肪を自分でらくらく下げる本
監修

-
管理栄養士HITOMI
管理栄養士。主にダイエットや食材の記事・監修・レシピ作成を行っています。