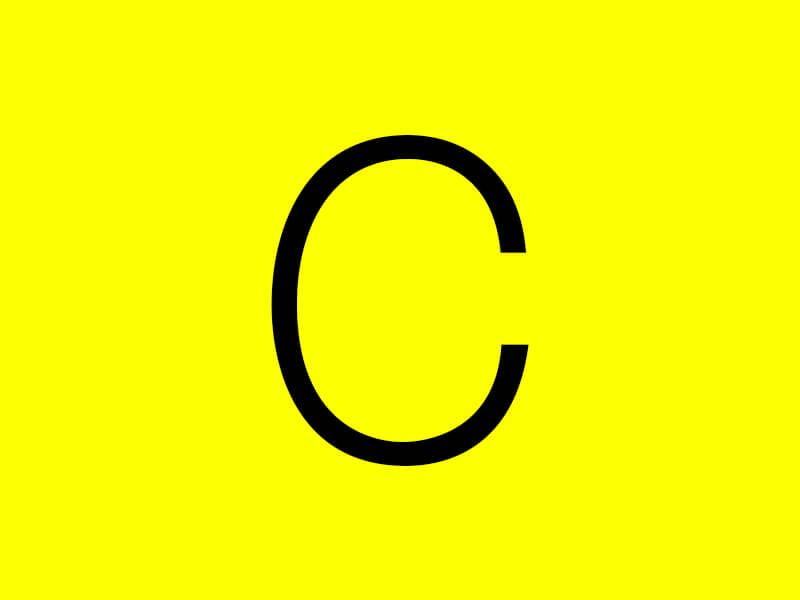ウリ科カボチャ属のカボチャは、β-カロテンなどの栄養がたっぷり。甘さがあり、和食はもちろん、グラタンやスープなどの洋食やお菓子作りにも大活躍します。
そんなカボチャの栄養と健康効果、歴史をまとめました。
スポンサーリンク
カボチャの起源
カボチャの原産地はアメリカ大陸です。
紀元前7000年~5500年頃のメキシコの洞窟の地層から、カボチャの種が発見されています。
日本カボチャは,、中央アメリカから南アメリカ北部の熱帯地方が原産地と言われています。
日本にこのカボチャが伝来したのは16世紀の中頃で、カンボジアに寄港したポルトガル船によって今の大分県に当たる豊後地方にもたらされました。この時、「カンボジア」がなまって「カボチャ」と呼ばれるようになったと言われています。
一方、現在主流になっている西洋カボチャの原産地は中央アメリカから南アメリカの高原地帯で、日本には19世紀中頃にアメリカから伝わったと言われています。本格的に栽培が始まったのは明治時代で、東北や北海道で生産が増えていきました。
カボチャの種類
現在日本で栽培されているカボチャは、「日本カボチャ」「西洋カボチャ」「ペポカボチャ」の三種類です。
「日本カボチャ」はねっとりした食感で醤油との相性が良く、その名の通り煮物などの和食に向いています。
日本の食文化の洋風化とともに「日本カボチャ」は「西洋カボチャ」にとってかわるようになり、今では西洋カボチャが主流になっています。甘味が強く、ホクホクした食感が特徴です。
「ペポカボチャ」はそうめんカボチャ、ズッキーニなどで、淡白な味わいが特徴です。
カボチャの旬と産地
夏からハロウィンの季節である秋がカボチャの収穫期です。
西洋カボチャの場合は、収穫後3ヶ月程度寝かせると熟成して甘みが強くなり、美味しくなります。
昔から、日本では冬至の日にカボチャを食べると風邪をひかないと言われていますが、それは旬の時期に収穫し、寝かせて熟成された食べ頃のカボチャに、栄養がたくさん含まれていることを表しています。
カボチャの収穫量が断トツに多いのが北海道で、他にも鹿児島や茨城、長崎、宮崎などで生産されています。
11月~5月にかけては国内産が品薄になるため、ニュージーランドやメキシコなど外国産のものが出回ります。
良いカボチャの選び方
良いカボチャは皮がかたく、形が左右対称で、ヘタがしっかり乾燥しています。
ヘタの周りが少しへこんでいる、あるいは皮にオレンジ色の部分がある場合は、完熟していることを示します。

カットカボチャを買う場合は、果肉の色が濃くて肉厚で、種とワタが詰まっているもの、種がふっくらしているものを選ぶと良いでしょう。
カボチャに含まれる栄養素
カボチャにはβ-カロテンが豊富に含まれているほか、カリウムやビタミンEをはじめとするビタミン類、食物繊維などの栄養素を多く含みます。
日本カボチャよりも西洋カボチャの方に栄養素が多く、特に、西洋カボチャには日本カボチャの約5倍ものβ-カロテンが含まれています。
β-カロテンが含まれる他の野菜については、「β-カロテンが豊富な野菜ベスト10」で確認しましょう。
カボチャによる健康効果
免疫力の向上
β-カロテンには、体内の粘膜の細胞を強化して免疫力を高める働きと、体を酸化から守る抗酸化作用があります。
また、ビタミンCによる白血球の機能促進や抗ウィルス作用により、風邪やインフルエンザから体を守ります。
免疫力の向上に有効な野菜としては、他に以下が挙げられます。
β-カロテンを多く含む野菜としては、他に以下があります。
ビタミンCを多く含む野菜としては、他に以下があります。
冷え性を改善する
カボチャに豊富に含まれるビタミンEにより、末梢血管が拡張することで血液の流れが良くなります。
そのため血行不良を改善し、冷え性や肩コリなどの改善に役に立ちます。
冷え性改善についてはヒントを以下にまとめてみましたので、併せてご覧ください。
便秘やむくみの解消、高血圧予防
カボチャには不溶性食物繊維が多いため、便のカサを増やし腸の動きが促進されることにより、便秘解消に役立ちます。
便秘解消に効果がある野菜としては、他に以下の野菜があります。
便秘解消については、ヒントを以下にまとめてみましたので、併せてご覧ください。
また豊富に含まれるカリウムの働きにより、体内にあるナトリウムの排泄が進み、むくみの解消や高血圧の予防・改善への効果も期待できます。
むくみ解消については、ヒントを以下にまとめてみましたので、併せてご覧ください。
高血圧予防についてはヒントを以下にまとめてみましたので、併せてご覧ください。
カリウムが含まれる他の野菜については、「カリウムが豊富な野菜ベスト10」で確認しましょう。
美肌を保つ
β-カロテンとビタミンEの抗酸化作用により老化を防止し、ビタミンCにより美肌を保つ効果が期待できます。
さらに、β-カロテンが体内でビタミンAに変換されることで、皮膚や粘膜を正常に保つ働きがあります。
カボチャのおすすめ調理法
カボチャの調理法としておすすめなのが、油と一緒に調理すること。
なぜなら、β-カロテンとビタミンEは油と一緒に調理することで、吸収率がアップするからです。
また、普段は捨ててしまう「わた」の部分には、果肉の5倍ものβ-カロテンが含まれていますから、なるべく「わた」を捨てないようにするのもポイントです。

カボチャの天ぷらをしたり肉類と一緒に油で炒めたりすることで、栄養たっぷりでホクホクしたおいしいカボチャ料理を味わうことができるでしょう。