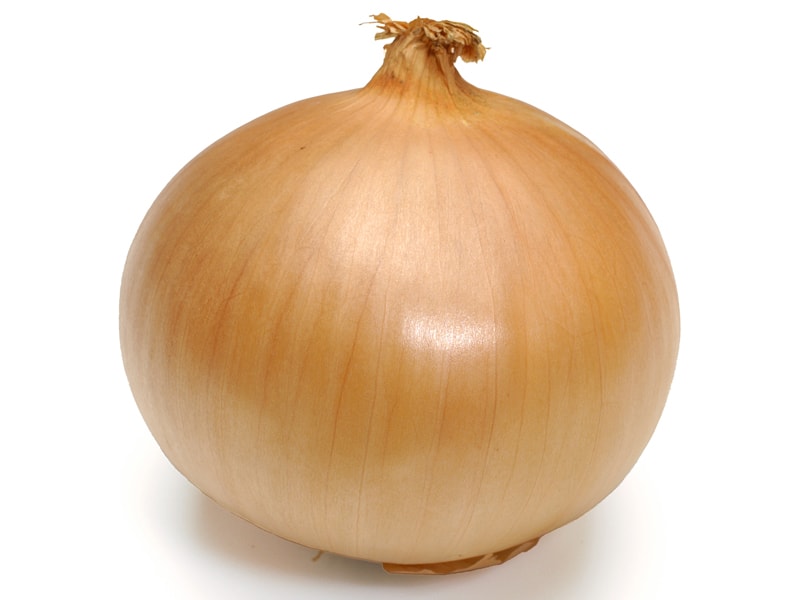キク科ゴボウ属に属するゴボウは、食物繊維が豊富な根菜です。キンピラやサラダ、スープなどとして調理されます。
そんなゴボウの栄養と健康効果、歴史をまとめました。
スポンサーリンク
ゴボウの起源
ゴボウの原産地はユーラシア大陸北部で、ヨーロッパやシベリア、中国の東北部にかけて、広く自生しています。中国では古くから薬用として使用されていました。
日本にいつ伝わったのかは定かではありませんが、日本でも中国と同様に薬用として使用されていました。平安時代の書物「本草和名」や「和名抄(わみょうしょう)」に登場します。
江戸時代になると広く食されるようになり、品種改良も進みました。ゴボウを食用としているのは、世界でも日本と台湾や韓国などの一部のみです。
ゴボウの種類
現在主流になっているのは「滝野川ゴボウ」と呼ばれる、長さが約1メートル、直径が2~3センチほどのゴボウです。

「新ゴボウ」は初夏に出回ります。直径が1.5センチほどで、細くて柔らかく、柳川鍋には欠かせません。
「堀川ゴボウ」は、京都堀川で滝野川ゴボウを特殊栽培した高価なゴボウです。長さが約50センチ、直径は6~9センチにもなり、中に空洞があります。
千葉県匝瑳市大浦地区で栽培されている「大浦ゴボウ」は直径が10センチにもなり、大きいもので重さが4キロほどになります。中に空洞があります。
「葉ゴボウ」は5月~6月に関西に出回ります。香りが良く、柔らかい葉柄と、若い根を食べます。
ゴボウの旬と産地
ゴボウの旬は、9月から12月にかけてです。主な産地は青森県、茨城県、北海道です。
良いゴボウの選び方
良いゴボウは弾力があり、先端にかけて緩やかに細くなっています。土付きの方が、風味が損なわれておらず日持ちもします。
ひび割れや黒ずみがあったり、しおれていたりするものは鮮度が落ちています。
太すぎるゴボウは、中に空洞がある場合もありますので注意しましょう。
ゴボウに含まれる栄養素
ゴボウに含まれる栄養素と言えば、何と言っても食物繊維です。ゴボウ100g中に約6g含まれています。水溶性食物繊維の「イヌリン」や不溶性食物繊維の「リグニン」が含まれます。
他にもカリウムや葉酸、強い抗酸化作用を持つポリフェノールの一種である「サポニン」「タンニン」や「クロロゲン酸」が含まれています。
ゴボウによる健康効果
腸内環境の改善と便秘解消
ゴボウと言えば、食物繊維が豊富で便秘解消に役立つというイメージですよね。ゴボウには水溶性食物繊維の「イヌリン」と不溶性食物繊維の「リグニン」がバランスよく含まれているので、便秘解消の効果が期待できます。
また、腸内の善玉菌を活性化させる「オリゴ糖」も含まれているので、腸内環境を改善してくれることも、便秘解消につながります。
水溶性食物繊維は悪玉コレステロールを体外に排出するよう働きかけたり、血糖の急激な上昇を防いでくれます。そのため、糖尿病予防にも効果が期待できますし、大腸がんの予防にも効果が期待できます。
便秘解消に有効な野菜は、他に以下があります。
便秘解消については、ヒントを以下にまとめてみましたので、併せてご覧ください。
むくみの緩和や高血圧の予防
ゴボウの水溶性食物繊維「イヌリン」には利尿作用があり、体内に溜まった水分や老廃物を排出させる働きがあるため、むくみが緩和します。
また、ゴボウに多く含まれるカリウムも、むくみを緩和させてくれます。カリウムはむくみ緩和の他に、高血圧の予防にも効果が期待できます。
むくみ解消に効果が期待できる野菜としては、他に以下が挙げられます
むくみ解消についてはヒントを以下にまとめてみましたので、併せてご覧ください。
高血圧予防についてはヒントを以下にまとめてみましたので、併せてご覧ください。
カリウムが含まれる他の野菜については、「カリウムが豊富な野菜ベスト10」で確認しましょう。
老化予防効果
ゴボウには、ポリフェノールの一種である「サポニン」「タンニン」「クロロゲン酸」が含まれていますが、これらの成分は抗酸化作用が高いことが特徴です。
ストレスや加齢によって発生した活性酸素は肌や内臓の老化を早めますが、強い抗酸化作用により老化現象を抑えてくれます。
ゴボウのおすすめ調理法
ゴボウはアクが強いため、たわしで皮をよくこすったり、水にさらしたりすることが多いと思います。しかし、ゴボウの風味やうまい成分は皮の部分に多く含まれますから、皮をこすりすぎない方が良いのです。
また、ゴボウを水につけると水が黒くなりますが、これはゴボウからポリフェノールが流れ出ているためです。ですから、あまり長時間水につけすぎない方が良いでしょう。
調理中にゴボウの変色を防ぐためには、酢水に浸けると良いです。
ゴボウは油と相性が良いので、キンピラや炒め物、揚げ物にもぴったりです。アイディアや組み合わせ次第で、色々な表情を見せてくれる野菜の1つです。